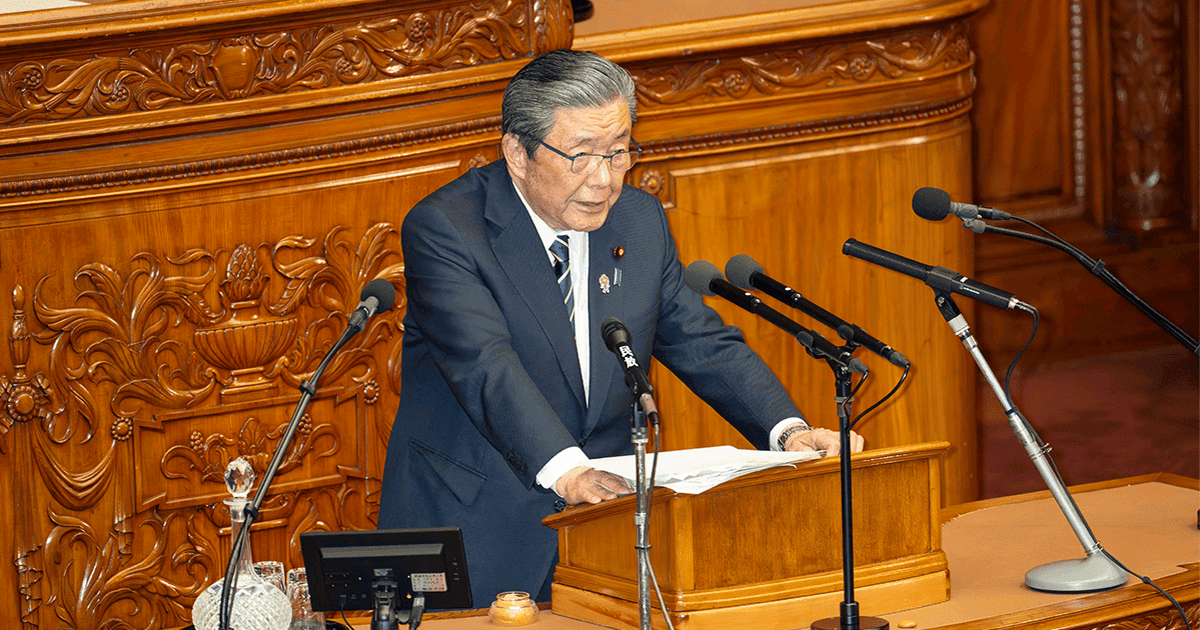
代表質問を行う森山裕幹事長
自由民主党の、森山裕です。
私は、自由民主党・無所属の会を代表し、石破総理の施政方針演説に対して質問いたします。
【はじめに】
今、厳しさを増す安全保障環境や、激甚化する自然災害、急速に進む人口減少など、我々は大きな時代の転換点にいます。様々なリスクが増え、先行きの見えない不確かな時代とも言われています。
しかし、未来は与えられるものではなく、自ら創っていくものです。今の時代を生きる我々が、その「不確かさ」を「可能性」に変え、国民一人ひとりがそれぞれの未来を自らの手で描くことができる、可能性に満ちた社会を創っていくべきです。
石破総理は、「楽しい日本」の実現を掲げられています。これまでの「強さ」や「豊かさ」から「楽しさ」へと価値観を大きく転換する、全く新しい国のあり方だと思います。なぜ今、「楽しさ」という価値観が重要であり、「楽しい日本」を目指すべきなのか、まず、総理の思いを伺います。
その上で、我々はこれまで、安倍政権、菅政権、岸田政権と、政権の基本姿勢を継承しながら政策を進めてきました。石破政権においてもその姿勢は全く変わらないものだと理解しておりますが、石破政権の基本姿勢についても、改めて伺います。
【経済】
我々が政権に復帰して以来、一貫して目指してきたのは、日本経済における成長と分配の好循環の実現です。昨年、株価はバブル期以来の高値となり、30年ぶりとなる大幅な賃上げや、過去最高となる設備投資など、好循環は間違いなく生まれています。
今、もっとも重要なのは、経済の好循環を国民生活に実感としてつなげていくことです。日本経済を新たなステージへと移行させ、好循環社会を実現する正念場を迎える中で、経済再生に向けた総理の決意を伺います。
(賃上げ)
好循環を実現するにあたって欠かせないのが、持続的な賃上げです。これまで政労使が一体となって賃上げを進め、2年連続で大幅な賃上げを達成しました。また、基本給にあたる所定内給与は平成4年以来の高い伸びとなり、最低賃金も全国平均で初めて1000円台に引き上げられるなど、賃上げは確実に加速しています。他方、足元では物価高騰が国民生活に大きな影響を及ぼしています。
経済の要は、物価と賃金が「循環」することです。物価高が悪いのではなく、物価に賃金が追いついていない状態であることが、そもそもの課題であり、物価高に負けない賃金を作っていくことで、経済の好循環を国民に実感していただかなければなりません。
手取りを増やすことも重要ですが、真に好循環を実現するためには、持続的な経済成長によって所得が増え続ける社会をつくっていくことが求められると思います。国民が暮らしの安心とゆとりを感じられる経済の実現に向けて、どのように取り組んでいかれるか、総理のお考えを伺います。
(中小企業の賃上げ)
経済の好循環を国民一人ひとりに感じていただくためには、中小企業・小規模事業者における賃上げなど、賃金上昇のすそ野を広げていくことが不可欠です。しかしながら、未だ中小企業・小規模事業者の賃上げ率は、大企業に比べ低い水準となっています。
賃上げ原資の確保には、適切な価格転嫁が求められますが、中小企業の価格転嫁率は4割にとどまり、全くできない企業も2割にのぼるなど、燃料費や人件費の増加分を価格に転嫁できていない、厳しい状況が続いています。
わが国企業の99.7%を占め、国の経済の根幹を支える中小企業・小規模事業者の賃上げは、必要不可欠です。今後、中小企業・小規模事業者においても力強い賃上げを実現していくことが重要と考えますが、環境整備に向けた総理のご所見を伺います。
(投資)
成長型の経済へ移行し、好循環を実現させるためには、積極的な投資も不可欠です。わが国では、国内投資が30年ぶりに100兆円を超えるなど、高い投資意欲が醸成されてきています。この流れをさらに加速させるため、一層の官民連携を進め、特にAIや半導体、量子や宇宙といった成長分野や戦略分野における投資の拡大を図っていくべきです。
石破政権は、AIや半導体分野に10兆円を超える公的支援を行い、今後10年間で50兆円の官民投資につなげる方針を掲げています。
スマホや家電など、産業や生活のあらゆる部分で使われているAIや半導体は、デジタル社会に欠かすことのできない重要な物資であり、国内での生産基盤強化はまさに喫緊の課題です。
現在、北海道では、国産の次世代半導体の生産に向けて、ラピダスの工場建設が進んでいます。九州では、熊本県へのTSMCの進出を契機に、多くの半導体関連企業の進出や拡大が進んでおり、九州全体への経済波及効果は、10年間で20兆円を超えるとも言われています。
社会課題を解決し、人々に安心とゆとりをもたらす「盾」でもあり、また経済の拠点として、活力ある地域づくりの「糧」でもある成長分野や戦略分野について、政府の強力な後押しの下、官民が連携しながら、付加価値の創出に積極的に取り組んでいくべきと考えますが、総理のご所見を伺います。
【安全保障】
次に、安全保障政策について伺います。
安全保障とは、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために、有事に備え、あらゆるリスクから国民の生命や財産を守り抜くことです。いつ起こるか分からないからこそ、平時から万全の準備を進めておかなければなりません。
(防衛力強化)
まず、防衛力の強化についてです。わが国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑な状況にある中で、防衛力の抜本的強化を真に実現するためには、その担い手である自衛官が、国家の防衛という任務に専念できるよう、必要な態勢整備を速やかに進めていかなければなりません。
石破政権において昨年、自衛官の処遇や勤務環境の改善、新たな生涯設計の確立に向けた「基本方針」が策定されました。今後、自衛官が、国の安全を保つという任務に誇りと名誉を感じられる処遇の確立に向けて、具体的にどのように取り組んでいくお考えか、総理のご所見を伺います。
(経済安保)
経済安全保障を揺るがす事案は、近年、ますます巧妙化しています。本年は、経済安全保障推進法の3年見直しやセキュリティ・クリアランス制度の運用開始が予定されていますが、国際情勢が目まぐるしく変化する中で、わが国の経済安全保障を確保し、国民の安心・安全を守り抜くためには、常に先手で対応していかなければなりません。経済安全保障のさらなる強化について、経済安全保障担当大臣に伺います。
(サイバー安全保障)
通信・情報技術の発展により、我々の社会は、いつでも、どこでも、誰とでもつながることができる、利便性の高いものとなる一方、偽情報の拡散やサイバー攻撃など、デジタル技術が生活を脅かすリスクにもなるという課題が生じています。
特に、重要インフラの機能停止や破壊などを目的とした重大なサイバー攻撃は、国家を背景とした形でも既に日常的に行われており、わが国の安全保障の大きな懸念となっています。社会全体がデジタル技術の恩恵を受ける中で、国民の安心・安全を確保するためには、サイバー安全保障の強化が急務です。
近年、巧妙化や高度化が進むサイバーの脅威から国民の生命や財産を守り抜くためには、官民や国際社会とも連携しながら、受けた攻撃に対処するだけでなく、脅威そのものを未然に排除する態勢も整えていくべきと考えますが、いわゆる「能動的サイバー防御」に向けた態勢整備を、今後どのように進めていくお考えか、総理に伺います。
また、急速な技術革新が進む生成AIの適正かつ透明な利用に向けた環境整備への取組みについて、併せて伺います。
(食料安保)
世界的な人口増加による需要の増大、国際情勢や気候変動による生産の不安定化など、農林水産業を取り巻く環境は今、大きく変化しています。さらに国内では、今後20年で農業者が90万人近く減少するなど、農業の担い手不足も深刻となっており、食料の安定供給に対する国民の不安は一段と高まっています。
政府は、昨年の「食料・農業・農村基本法」の改正を受けて、今後5年間で集中的に施策を実行し、農業の構造転換を図っていく方針であると承知しています。わが党でも、「食料安全保障強化本部」を新たに設置し、現場の声にも耳を傾けながら、食料安全保障の強化に向けた議論を行なっています。
わが国の食料安全保障を確保するためには、持続可能な農業の実現に向けた十分な予算の確保と、関連施策を充実させることが不可欠です。そしてそのためには、国土強靭化のための「5か年加速化対策」のように、必要な事業量や予算額について中長期的な見通しを持って取り組む必要があります。
持続可能な農業と食料の安定供給のために特に重要なのは、農産物や食品の合理的な価格の形成です。農産物や食品は、市場原理のみに価格形成を任せていては、農業者の収入が安定せず、生産基盤の弱体化につながる懸念があります。特に肥料や燃料の価格が高騰する中、持続可能な食料システムを実現するためには、消費者の理解も深めながら、生産から消費までの各段階の関係者が協調することで、合理的な費用を考慮した価格形成を進めていくべきあり、政府において責任を持ってこれを実現していく必要があると考えますが、農林水産大臣のご所見を伺います。
(エネルギー安保)
エネルギーは、国民生活や経済活動の基盤となるものです。近年、デジタル化によって、わが国の電力需要は増加に転じており、2050年までにさらに40%増えると見込まれています。また、AIや半導体といった将来の成長産業や、鉄鋼や化学といった素材産業は、いずれも大きなエネルギーを必要としており、安定供給は急務です。
一方、わが国のエネルギー自給率は13%と先進国で最も低く、資源国のロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の不安定化を受け、エネルギーに対する国民の不安が高まっています。さらに、世界では脱炭素に向けた機運が急速に高まっており、脱炭素電源の確保も不可欠です。
こうした中、わが国のエネルギー安全保障を確保するためには、再生可能エネルギーや原子力などを最大限活用し、特定のエネルギー源に過度に依存しない分散化の取組みを進めることで、有事にもしっかりと機能する万全のエネルギー供給体制を整えていくことが重要です。国民の安心・安全に資するエネルギーの安定供給に向けて、今後どのように取り組んでいかれるお考えか、経済産業大臣に伺います。
(防災・減災)
阪神・淡路大震災の発生から30年を迎えました。災害対応は、災害が起こる「前」がもっとも重要であり、平時からの備えを万全にすることで、被害を最小限にとどめることができます。そのために、防災インフラの整備といったハード面と、新たな技術を活用した情報の分析や発信といったソフト面の両面で、事前防災の態勢を十分に整えておかなければなりません。本年は、国土強靭化5か年加速化計画の最終年となりますが、加速化計画に盛り込まれた取組みを着実に実施するとともに、その後も切れ目なく、中長期的な見通しの下で、必要な施策を計画的かつ着実に推進していくことが重要です。
事前防災の大きな取組みの一つとして、石破総理が進めているのが「防災庁」の設置です。災害対応の司令塔として期待される一方で、新たな機関を設置しなくても、今ある組織体制を活用することで十分足りるのではないか、との声も聞かれます。
しかしながら、激甚化する自然災害が次々と発生し、南海トラフ地震や首都直下地震といった大規模災害の発生も懸念される中、平時からの備えと、有事の際にどこが責任を持って対応にあたるのかを明確にしておくことは、国民の混乱を避けるためにも、極めて重要なことだと思います。改めて、防災庁設置の必要性について、国民の皆様に分かりやすい形で、総理からご説明をお願いいたします。
【人口減少社会】
わが国の人口は、平成23年以降、13年連続で減少し、その減少幅は年々拡大しています。また、出生率は過去最低になる一方、高齢化率は世界で最も高く、少子高齢化が急速に進んでいる状況です。さらに、31の道府県で人口の流出が拡大し、東京圏への転入が強まるなど、都市部への一極集中も深刻な課題となっています。
2100年には、わが国の総人口は現在の3分の2になるとも言われており、今後我々は、規模の大小ではなく、少ない人口でも多様性に富んだ、成長力のある社会を目指していくべきです。
(地方創生)
石破総理は、地方創生の初代担当大臣として、これまで地方創生の推進に尽力されて来られました。そして昨年、都市と地方が結びつくことで、社会の在り方を大きく変える「日本創生」の実現を目指し、今後10年間の基本構想の策定や、地方創生の交付金を倍増するなど、新しい地方創生の取組みを進めています。
東京であれ地方であれ、各地域がそれぞれの特徴を活かし、自律的で持続的な社会を創生するためには、「安心して暮らせる環境」と「活力ある地域づくり」が必要です。
私の地元で、10年以上にわたってリサイクル日本一を達成している鹿児島県大崎町では、町の取組みを発展させ、民間企業や学校、メディアとも連携しながら、SDGsの達成や地域の課題解決に向けた様々なプロジェクトを展開しています。企業からは、企業版ふるさと納税を活用して3億円以上の寄付が集まり、今では「大崎町モデル」として、世界からも大きな注目を集めています。
また曽於市では、鹿児島大学と連携し、地方が抱える人口減少と、大学が抱える実習先不足という双方の課題を解決するために、全国で初めて獣医学の実習先拠点が整備されました。企業からは2億円以上の寄付が集まり、県からは県立高校の跡地を無償で譲渡されるなど、国や県、市、企業や大学などとも連携しながら進められ、全国の獣医学生の実習先拠点にとどまらず、地域活性化や畜産の振興の拠点としても大きな期待が寄せられています。
「地方こそ成長の主役」である所以は、地方をもっとも理解しているのは、その地域に携わる方々だからです。地域を構成する様々な分野の人たちが連携しながら、それぞれの魅力を最大限に活かした地方創生の取組みを進めていくことが重要であり、国の力強い後押しによって、あらゆる自治体や民間も巻き込みながら、全ての人が希望と幸せを実感できる社会を日本全体で創っていくべきと考えますが、新たな地方創生の推進に向けた総理のご所見を伺います。
【外交】
本年は、戦後80年の節目を迎えます。わが国は、戦後一貫して平和国家として歩みを進め、世界の安定と繁栄に力を尽くしてきました。しかし今、ウクライナや中東情勢に加え、先進国でも政治体制が不安定となるなど、世界各地で対立と分断が生じてきています。
(米国)
日米同盟はわが国外交・安全保障の基軸であり、インド太平洋地域における平和と繁栄の基盤です。しかし、そのアメリカで誕生したトランプ政権は、これまでの政策を大きく転換し、「自国第一」の姿勢を強めています。
世界は今、エネルギーや気候変動といった複合的な危機に直面しており、体制や価値観を超えた協調が一段と求められています。特に、欧州や中東で戦火が上がっている現状を鑑みれば、東アジアを含むインド太平洋地域の安定はかつてないほど重要なことは明らかです。これまで以上に、日米の協力関係をさらに強化し、自由で開かれた国際秩序をともに守り抜いていかなければならないと考えますが、総理にトランプ政権との向き合い方について伺います。
(中国)
わが国周辺では、軍事力拡大を推し進める中国や、弾道ミサイル発射を強行し続ける北朝鮮など、国際秩序の根幹を揺るがしかねない事態が数多く発生しています。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序は 平和と繁栄の礎であり、世界のどこであれ、力による一方的な現状変更の試みは許されません。
私は今月、中国を訪問し、6年3か月ぶりの開催となる「日中与党交流協議会」において、世界情勢が変動する中、国際法に基づく国際秩序を堅持するため、両国が担うべき責任と役割について、率直な意見交換を行なってまいりました。
日中関係において重要なのは、対話を欠かさず、お互いに知恵を出し合いながら、課題や懸案を減らし、協力と連携を増やしていくことだと思います。わが国として守るべきものはしっかりと守りつつ、建設的かつ安定的な日中関係の構築に取り組んでいくべきと考えますが、総理のご所見を伺います。
【憲法改正等】
憲法は、国のあるべき姿を示す国家の基本法であり、社会構造や国民意識の変化に応じて、必要な改正を行なっていかなければなりません。時代環境が大きく変わる中、新たな時代にふさわしい憲法のあり方について広く議論し、国民とともに、改正の早期実現に取り組んでいくべきと考えますが、総理のご見解を伺います。
また、民主政治を進める上で重要な役割を担う政党について、いわゆる政党法を含め、政党や政治団体としての規律のあり方をどのように考えていくべきか、併せて伺います。
【万博】
本年は、4月から大阪・関西万博が開幕します。私も先週、現地を視察してまいりましたが、夢あふれる未来の日本を世界中の人たちに味わってもらう絶好の機会だと強く感じました。成功に向けてどのように取り組まれるか、総理に伺います。
【結びに】
大阪・関西万博では、メインテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」とともに、「多様でありながら、ひとつ」という理念が掲げられています。
多様であるが故に衝突や摩擦も起こりやすい世の中ではありますが、だからこそ、一人ひとりが多様な未来を追求できる可能性にあふれた社会を創り、令和の時代にふさわしい、美しい調和を皆で目指すべきです。
明治維新の際、私の郷里の偉人、西郷南洲翁は、「厚き徳をもって新しい政をなすべきである」という『新政厚徳』の4文字を掲げました。多くの変化を伴う不確かな時代を生きる我々は、これまで以上に、謙虚に丁寧に、政治に臨んでいかなければなりません。このことを申し上げ、質問を終わります。






















