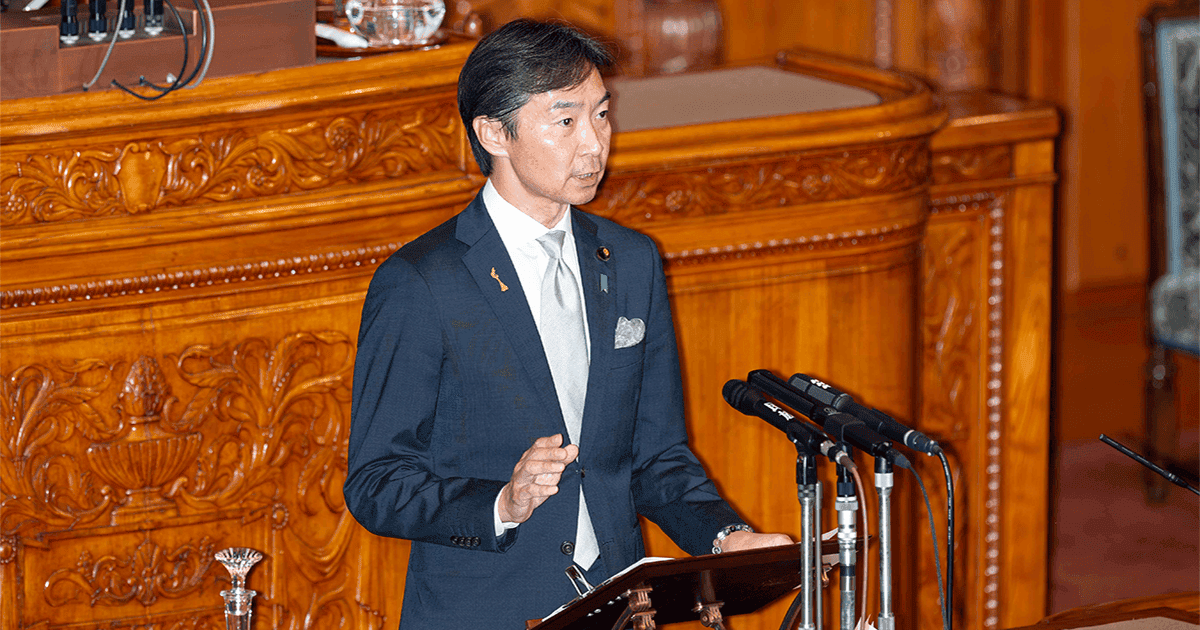
代表質問に臨む宮本周司参議院議員
自由民主党の宮本 周司です。
会派を代表して、石破総理の所信表明演説、とりわけ令和6年能登半島地震と9月の奥能登豪雨災害を中心に質問致します。
本年元日に、私の地元石川県では、能登半島地震が発生しました。9月21日には線状降水帯が発生し、奥能登では観測史上最大の猛烈な雨が降り、気象庁は石川県に対して初めて大雨特別警報を出しました。
被害が出ないことを願いながら、地元での報道や情報を確認しておりましたが、時間が経つ毎に事態は深刻化し、筆舌に尽くし難い被害が広がってしまいました。
これまで、能登半島地震や奥能登豪雨災害をはじめ、梅雨期から続く大雨や台風による災害も発生し、多くの尊い命が失われました。犠牲になられた方々に心から哀悼の誠を捧げますとともに、最愛の家族を亡くされた御遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上げます。
そして、被害に遭われた全ての方々に、衷心よりお見舞い申し上げます。
能登半島地震の発生当時、私は自民党の県連会長を務めており、すぐに県内にある全ての政党支部に呼びかけ、それぞれに寄せられる情報や声が災害対策本部に集中して指揮系統が混乱しないよう、我々に一元化することをご提案しご理解とご協力をいただきました。
情報が錯綜することがない状態をつくり、日々寄せられる内容には、整理して災対本部につなぎ、私から各政党支部代表者に都度、回答や報告をさせていただき、政党の垣根を越えて連携し、被災地に寄り添った対応を実践できました。
そのことには、各政党の国会議員皆様のご理解とお力添えもあったと思います。衷心より感謝申し上げます。
また、今回の豪雨災害においても自衛隊、警察、消防、海上保安庁をはじめとする関係機関、全国の自治体からの応援職員、様々な工事関係者、そして多くのボランティアの方々に、被災地や被災者へお心やお力をお寄せいただいていることにも深く感謝致しております。
この奥能登豪雨は、震災から何とか立ち上がろうと、能登の皆様が一歩、また一歩と復旧に向けて進みだした矢先のことでありました。
発災から二日後、浸水した仮設住宅や避難所に伺いました。
「なんで能登ばっかりこんなことに」、
「地震の時よりもひどい」、「心が折れた」、
「もう、どうしてええか分からん」、「最悪の年や」、
不安を抱え、絶望の淵に立たされた被災者の声を聞き、これまでの能登の皆様の復旧復興に向けた努力やお気持ちも考えると、胸が張り裂けそうな思いでいっぱいになりました。
先週5日、石破総理には、就任後初の国内出張として、元日の地震や記録的豪雨に相次いで襲われた奥能登をご視察頂きました。
被災現場の惨状を目の当たりにし、被災された方々の悲痛な訴えを受け止めて頂きました。
「政治は国民のもの」
このような悲惨な状況に置かれた被災地の皆様に、光を届け、必要な取組みを着実に実践するという政治の役割を、いまこそ発揮すべきときであります。
そこで、総理、自らが訴える「国を守る」「国民を守る」「地域を守る」という信念の下、能登半島地震、さらに記録的な奥能登豪雨という複合災害に見舞われた方々、そして地域に対して、どのように寄り添っていくお考えでしょうか。必ずや能登を復興するという決意とともに、お伺いします。
元日の地震によって、大量の土砂が川をふさいで水の流れをせき止める河道閉塞、いわゆる土砂ダムが多く発生しましたが、今回の大雨災害で半分ほど消滅したことが確認されています。
土砂ダムにあった大量の水や土砂、流木が、記録的な豪雨とともに流れ出したことで、今回の災害被害がより深刻化したと考えられます。
すでにテックフォースが派遣され、被害状況を調査していると思いますが、能登半島地震による被災の影響が、今回の大雨による災害のパワーを増幅させ、被害規模を拡大させていることは明らかです。
このような複合災害の様相を呈する被害の中で、水害のみの被害を切り分けることは困難です。仮に切り分けたとしても、補助事業の水準が異なれば、被災自治体であったり被災した皆さまに無用の負担と不安をもたらすことになります。
そこで、今回の豪雨災害については、複合災害として能登半島地震と一体的かつ同水準の取扱いとし、能登半島地震向けの様々な支援制度も包括的に適用できるようにするべきと考えますが、総理のご見解をお聞かせください。
能登半島地震、そして奥能登豪雨という複合災害は、一次産業にも大きな被害をもたらしています。
例えば、奥能登では前年の水稲作付面積に対し約三分の一の農地が冠水し、河川などからの土砂や流木の流入がありました。速やかな応急復旧を行わなければ、今後の営農継続の意欲が失われてしまいます。
また、山地においても、地震により緩んだ斜面が豪雨に見舞われ、新たな崩壊や地すべり、土石流が多数発生しています。国も制度の枠を超えて、積極的な人的、技術的支援を行うべきと考えます。
総理のご地元・鳥取県や石川県など日本海側では、11月にズワイガニ漁が解禁されます。それに向けて本格的に漁業を再開するべく、能登半島地震での隆起により変化した海底や漁港の機能を取り戻すための浚渫を進めてきましたが、大量の流入土砂や流木が、復旧途上の漁港に大きな影響を及ぼしています。
農業・林業・漁業という一次産業は、地方の基幹産業であり、地震、そして大雨と相次いで発生した複合災害による、この分野への大きな打撃は、地方の存亡に係わる問題でもあります。
来年の作付けに間に合わせる、カニ漁の解禁に間に合わせるなど、能登を支える農林水産業に従事する被災者の前向きな気持ちを支えるためにも、国として、復旧に必要な財政支援、技術支援等を強力に行っていただきたいと思います。そこで、今後の時間的な見通しも含めて、総理のお考えを伺います。
公共土木施設も住宅も深刻な被害を受けています。
地震の際はなんとか持ち堪えた家が、今回の土砂災害で崩れてしまった、あるいは、修繕をする前に豪雨が襲ったことで、被害が深刻化した家屋もございます。
地震の災害査定を進めているさなかに、大雨被害が重なったため、地震と大雨の災害査定の一体的実施や査定期間の延長も検討が必要です。
公共土木施設等の場合は、復旧に必要な予算の確保のための被災状況の再調査、住宅の場合は、罹災証明など建物被害認定の再調査が必要ですが、すでに自治体職員は手一杯です。国や全国の自治体からの派遣応援が更に必要です。
また、今後の自治体の災害対応力を強化することも踏まえれば、総務省の復旧復興支援技術職員派遣制度による支援対象を都道府県に広げるという検討も、喫緊の課題だと思います。
そこで、複合災害においては、被災自治体における査定作業等への配慮や人的支援の拡充など、被災自治体の立場にたった柔軟な対応が不可欠と考えますが、石破総理のお考えをお伺いします。
総理にご視察頂いた珠洲市大谷町や輪島市久手川町をはじめとし、多数の河川氾濫や大規模な土石流、地滑り等による被害が複雑に発生し、広範囲に甚大な影響が出ています。
道路も河川も住宅も田畑も土砂に埋まった状態から、迅速な復旧を実現するためには、事業所管省庁の枠を超えた一体的な対応が必要だと思いますし、多くの技術者や、より高度な技術力を有する国による権限代行が極めて有効だと考えます。
また、権限代行による工事や、国県が管理する工事以外にも広範囲な復旧事業が必要となります。それらは市町が担いますが、国への補助申請に当たり、場所や処理量に応じて異なる省庁への複雑な事務手続を要することになります。市町の負担を軽減するためにも、これらの事務処理をワンストップで行えるスキームの構築も必要と考えます。
石破総理、今回の被災地での権限代行による河川災害対策や土砂災害対策の実施についてどのようにお考えでしょうか。さらに、補助事業の復旧に係る申請事務について、市町の負担を軽減するための国の支援策についてもお尋ねいたします。
能登半島地震では、石川県、福井県、富山県、新潟県といった広い地域に液状化現象が発生し、建物が傾く、道路が波打つといった被害が出ました。
液状化や側方流動による被害には、被災した家屋だけでなく、埋設物も含めて面的に、地盤を固める薬液注入や地下水位を低下させる工法等による対応が求められます。
政府は、それら複数の工法に関する調査結果を整理し、今月中には市町に対して対策方針案を示すとしていますが、被災自治体においては、それを受けてからようやく年内をめどに復興計画の素案を作成する予定と聞いております。
液状化や側方流動による被害を受けた市民・町民は、なかなか具体的な対策方針が示されないため、長年暮らしてきた自宅、そして愛着のある地元で、再び安心して生活できる環境を取り戻すことができるのか、ずっと不安な気持ちに悩まされています。
液状化や側方流動は、復旧や対策に多くの時間を必要とする大きな問題です。国として、どのように液状化から地域を再建し、守っていくのか、総理にお伺いします。
予算措置について伺います。
能登半島地震では、人口規模の小さな市町が被災しており、求められる復旧事業や支援策が、河川や道路など公共土木施設の復旧から、被災者の生活やなりわいの再建に必要な予算まで多岐にわたり、かつ求められる局面が、地域によって異なっています。
そのため、市町の復旧・復興計画が定まり、それに基づく予算措置がはっきりするまでは、地域それぞれの場面や進捗状況に応じて、迅速かつ柔軟に事業を展開できる予備費が効果的だったと考えます。
そこで伺います。
政府においては、能登半島地震対応として、令和6年度予算における予備費を1兆円規模に拡大し、様々な措置を講じてきましたが、今後の本格復旧や創造的復興のフェーズを捉えると、補正予算も含めて、どのように予算を確保していくお考えでしょうか。
同時に、二重の被害を受けたことにより、災害対応がより長期化し、対応経費も嵩み、被災自治体の財政を圧迫することが想定されます。県や市町が躊躇することなく複合災害への取組みを進めることができるよう、政府が一丸となって被災地の復旧・復興の加速化に全力で当たる決意と覚悟がみえるような、思い切った対応が求められています。石破総理はどのようにお考えでしょうか。
能登の特色ある産業の衰退や更なる人口の流出が懸念されます。
能登半島地震に伴う雇用調整助成金の支給日数は、1年間で300日の特例措置となっています。
震災発生から10ヶ月目を迎えましたが、依然として、活動再開に至っていない事業者も多いです。
例えば、和倉温泉では一部の旅館が営業を再開していますが、多くは休業が続いています。これから大規模な修繕や、建物を解体したり新たに建設することに加え、温泉地全体も再建していかなければならないため、事業再開までの見通しもなかなか明確にすることができません。
助成金が完全になくなり、一旦離れた人が戻らなければ、旅館の営業再開は難しくなり、ひいては地域経済をけん引する温泉地や関連産業が衰退し、人口減少を加速させ、地方創生に逆行することも危惧されます。
同様の心配は、観光産業だけではなく、輪島塗などの伝統工芸や酒造業など、その土地に由来し、現在の場所でなければ事業の継続ができない多くの産業にも当てはまり、再建には数年を要すると見込まれます。
能登半島の経済・産業・雇用特性や豪雨による被災状況等を踏まえた上で、能登半島が創造的復興を成し遂げ、将来に向けて生き残るためにも、そして故郷に住み続けたいという住民の思いを守るためにも、政府において、雇用調整助成金の支給期間や日数の延長、今回の豪雨被害を受けた事業者を対象に加える等の措置が必要不可欠です。地方創生にこれまで取り組んできた石破総理はどのようにお考えでしょうか。
能登半島地震で被害を受けた一次産業、二次産業、三次産業のなりわいの再建に資する補助金・交付金が措置されたことで、折れかかった気持ちを何とか奮い立たせ、未来に希望を感じることができたという方は大勢いらっしゃいます。
一方で、それらの支援事業を利用し、損壊した施設や機材等を更新したものの、豪雨災害で再び被災してしまったという事業者や営農者も確認されています。このことにより、物的な損失のみならず、精神的に大きな打撃も受けております。
また、奥能登においては、一昨年の震度6弱の地震、昨年の震度6強の地震に加え、能登半島地震や大雨による被害が重なっており、二重三重で負担を強いられ、債務を抱えた事業者への、金融面でのさらなる支援も強く求められています。
まずは、豪雨災害で被災された方々をこれまでと同じ補助金や交付金等の対象とし、その利用においては何ら制約がない運用を実現する必要があります。
能登半島地震の被災から必死の思いで事業を再開したものの、今回の豪雨で再び被害に遭い、精魂尽き果て廃業を決めたという方もいらっしゃいます。
「こんなんなら頑張らんとけばよかった」
そんな嘆きの声を聞き、かける言葉が見つかりませんでした。
石破総理、今回のような複合災害による複雑な事態に対しては、なりわいの再建に資する各省庁所管の補助金・交付金が、事業再開の意欲ある方を支えるという趣旨を踏まえて、制約なく活用できるように対応すべきと考えますが、総理如何でしょうか。
併せて、自然災害により多重債務を強いられた事業者の負担軽減に貢献できる金融政策の具現化に関しても、お考えをお聞かせください。
被災地では、今回の豪雨災害が重なったことも影響し、復旧・復興が更に遅れるのではないかという懸念が広がっています。
能登半島地震からの復旧作業で、すでにマンパワーの確保が難しい状況でしたが、これに奥能登豪雨からの復旧作業が加わったことで、人手不足が深刻化しています。
一刻も早く生活再建を願う被災者のために復旧作業を引き受けたいが、人手不足や時間外労働規制との兼ね合いで難しく、やむなく仕事の要請を断ったという経営者も多く、今後、入札不調が増えないか心配しております。
一方で、働く方々からは、被災者のため、被災地のために頑張るから、仕事を受けて欲しいという声も経営者に寄せられています。
まさに、復旧・復興の役に立ちたい、仕事をしたい・仕事を出したいと思っても、成立しにくいジレンマに陥りつつあると思います。
そこで、地震や大雨被害からの一日も早い復旧・復興に向けて、災害復旧作業のような、社会的なニーズが高く、緊急性もあるものの、なかなか働き手が集まらないという状況をどう改善していくお考えでしょうか。総理にお伺いします。
次に災害関連死対策についてお伺いします。
被災地は、これから冬の季節を迎え、寒さや雪の影響が心配されます。
地震、そして豪雨により被災し、あるいは復旧途中にある住宅や公共施設が、雪による被害も受けることが懸念されます。道路ネットワークが復旧していないことで、大雪となれば、物流が途絶えてしまいます。冬に備えて、物流が長期間、混乱した場合に耐えうる備蓄が不可欠です。
そもそも、異なる自然現象の大規模な災害が重なったことにより、公費解体やインフラ復旧にも影響が生じて、医療機関へのアクセスが低下している上に、十分な医療環境や医療従事者、介護や福祉に従事する人材の確保が難しくなっています。
福祉避難所の閉鎖、福祉施設の復旧遅れも重なり、生活環境や健康状態の悪化が危惧されています。
災害関連死から命を守るために、国として、身体的にも精神的にも負担の少ない避難所の設置や、必要な物資・設備の備蓄を含む運営を具現化するべきだと考えます。また、有事に迅速に対応できる、地方自治体と関係団体や民間企業とが連携した資機材の備えなど、新たな仕組みづくりも含めて総理にお伺いします。
次に災害に強い半島振興に関してお伺いします。
能登半島地震と豪雨からの救命活動、復旧・作業等に時間を要しているのは、半島という地形的な特性による要因が大きいと思われます。
道路は平野部のようにネットワーク化されておらず、一部が被災すると、復旧作業を担う事業者はその先への移動が困難となります。電気や水道といったライフラインも多重化されていないことから、もし寸断するような状況になれば迂回して水や電力を供給することができません。
能登半島地震でも奥能登豪雨でも、通信の途絶が長引きました。
携帯電話の基地局が被害を受けたほか、電気の供給が止まったことで、基地局のバッテリーも時間の経過とともに落ちていき、通信の停波エリアが徐々に広がっていきました。通信が機能しなくなると、被災状況が把握できませんし、当然現地の被災された方々は情報すら入手できません。
平地が少なく、仮設住宅建設用の用地確保も簡単ではありません。今回発生した大量の土砂で埋め立てて用地にしてはどうかとの声も上がっています。
来年3月に半島振興法が期限を迎えますので、災害に対する脆弱性を改めて分析し、道路や電気、上下水道のネットワーク化や自家発電等による通信の強靭化も検討する必要があります。
次の半島振興法の改正では、能登半島地震・奥能登豪雨災害から得た教訓をどのように反映させ、災害に強い半島を目指していく考えなのか、総理にお伺いします。
石破総理、最後に申し上げます。
大規模な自然災害が発生する以前から、少子化・高齢化、そして過疎化が進んでいる能登地域ですが、被災後の数ヶ月でさらに多くの方々が故郷を離れており、人口流出が深刻化しております。
石破総理は「地域づくりは、人づくり」とおっしゃいましたが、能登半島では、その地域をつくる人がいなくなりつつあります。
このままでは、地域の復興を考える以前の問題として、そもそも地域が維持できるのかという不安を、被災地・被災者は痛切に感じておられます。
地方が置かれている状況の厳しさを、身をもって感じておられる石破総理だからこそ、災害に直面し、苦しみや不安に包まれている方々を勇気づけ、疲弊する地域に明るい未来が見えるようなメッセージを届けることができると信じています。希望を取り戻すための具体的な政策を確実に実践し、これからの復旧、そして創造的復興を全力で応援していただけるよう強くお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。






















