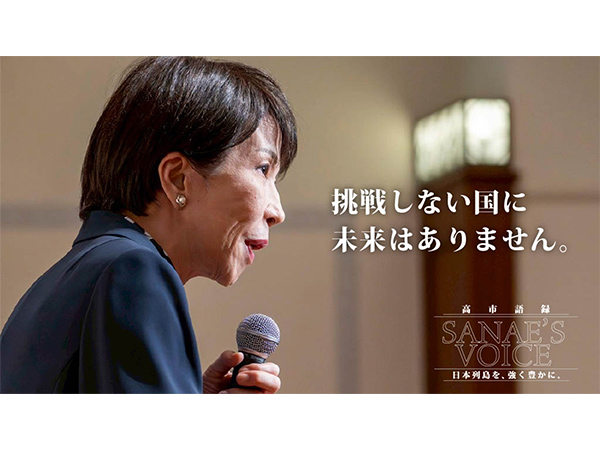急転直下で妥結した日米関税交渉。トランプ大統領との間の「ディール(取引)」についてどのような評価となるのでしょうか。日米関係や米国内政治にくわしいエコノミストの吉崎達彦氏による、「関税より投資」で得た合意内容についての寄稿を掲載します。
8月1日から「トランプ関税」の税率が変わった。日本の相互関税は10パーセントから15パーセントになり、分野別関税の一種である自動車関税は27.5パーセントから15パーセントに引き下げられる。鉄鋼・アルミニウム関税は50パーセントという高い水準のままである。対米輸出の税率は、全体として1年前に比べれば大きく引き上げられる。それでも事前に言われていた「25パーセント」や、それ以上にならなかったのは慶賀の至りである。
日本から米国への年間輸出額はおよそ21兆円。最大の輸出相手国であり、輸出全体の約2割を占める。なかでも約6.2兆円を占める自動車輸出は、わが国経済にとっては死活的に重要な意味を持つ。自動車部品の対米輸出も年間約1.2兆円あるが、特に中小の部品メーカーにとって15パーセントの税率は痛いかもしれない。
それでも7月23日に妥結した日米関税交渉の成果を多としたい。トランプ大統領という難しい相手に対し、赤澤亮正経済再生担当大臣を中心とする交渉チームはよく頑張った。米国側は当初、「相互関税だけが交渉対象」という姿勢だったが、日本側は分野別関税も交渉対象にすべきと主張し、自動車関税の引き下げを勝ち取った。米自動車業界からは、「これでは北米製よりも日本車の方が有利になる」と不満の声が出ている。
「合意文書がない」との不安はある。しかし、他の国もほとんど合意文書を作っていない。文書化する作業中にトランプ氏の機嫌を損ね、せっかくまとまった話が壊れてしまうことを恐れているのだ。また、米国側があまりにも多くの国との交渉を同時に抱えていて、単純に人手や時間が足りないという事情もある。
5月8日に最初の対米合意を果たした英国は、例外的に米国との間で簡単な枠組み合意文書を作っている。ただし法的拘束力はなく、議会が批准する必要もない。日本の場合も、将来的には同様な覚書をまとめる必要があるだろう。
長い日米通商摩擦の歴史の中でも、今回の交渉は画期をなした。これまではずっと関税を下げる交渉だった。ところがトランプ政権は一方的に関税を引き上げ、各国がそれをいかに思いとどまらせるか、という交渉になった。日本は最大の対米投資国であることを生かし、「関税より投資」をテコに譲歩を迫った。