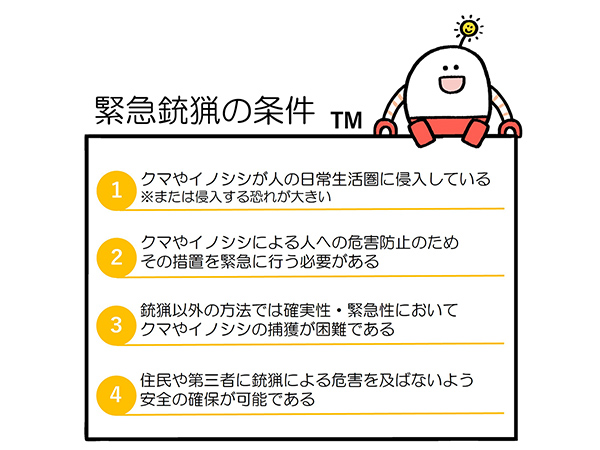国益を維持拡大していくために政治の安定が不可欠
平成28年と令和4年の新年号で、筆者は「自民党に期待する」として4点挙げた。具体的には、中長期的な「大戦略」を持つこと。海洋国家として、共通の利益を有する国々との海洋同盟の構築を進めること。諸外国との第2次大戦後の和解の努力を進めること。最後が、保守主義の進化である。
今もこの考えは変わらないが、過去2年間を振り返ると、日本を取り巻く外交・安保環境は再び予想を超える速度で変わり始めたようだ。ロシアがウクライナを侵略し、中東ではイスラム組織「ハマス」がイスラエルに奇襲攻撃を敢行した。いずれも多くの欧州・中東専門家の予想を超えた想定外に近い事件だった。
この2つの紛争は、決して独立・個別の事象ではない。それどころか、両紛争が相互に関連している可能性は高い。されば、現在欧州のウクライナで起きている悲劇と、中東のパレスチナ・ガザで起きている惨状は、過去10年ほどの間に、国際情勢に新しい潮流が生まれ、それが拡大し、新たな不安定期に入りつつあることの前兆かもしれない。
8年前筆者は当時の国際情勢について、「冷戦終了後四半世紀、ロシアが欧州の陸上で、イスラム国が中東や欧州で、そして中国がアジアの海上でやっていることは、いずれも醜い民族主義的・宗教的野心が、現状に不正義を見出し、力を以てその現状を変更しようとする企てであり、いずれも受け入れられるものではない。」と書いた。
さらに2年前筆者は、「近年米国の外交・安全保障政策は再び変化し始めた。第2次大戦後の東西冷戦時代に欧州中心だった米国外交の優先順位は、1990年代以降、中東に移り始め、その傾向は2001年以降『テロとの闘い』で加速された。ところが最近は、中国の台頭に伴って米国外交の優先順位が再び変化し、今や『インド太平洋』地域に移り始めたようだ」とも書いている。
令和6年の今、筆者は次のように考えている...