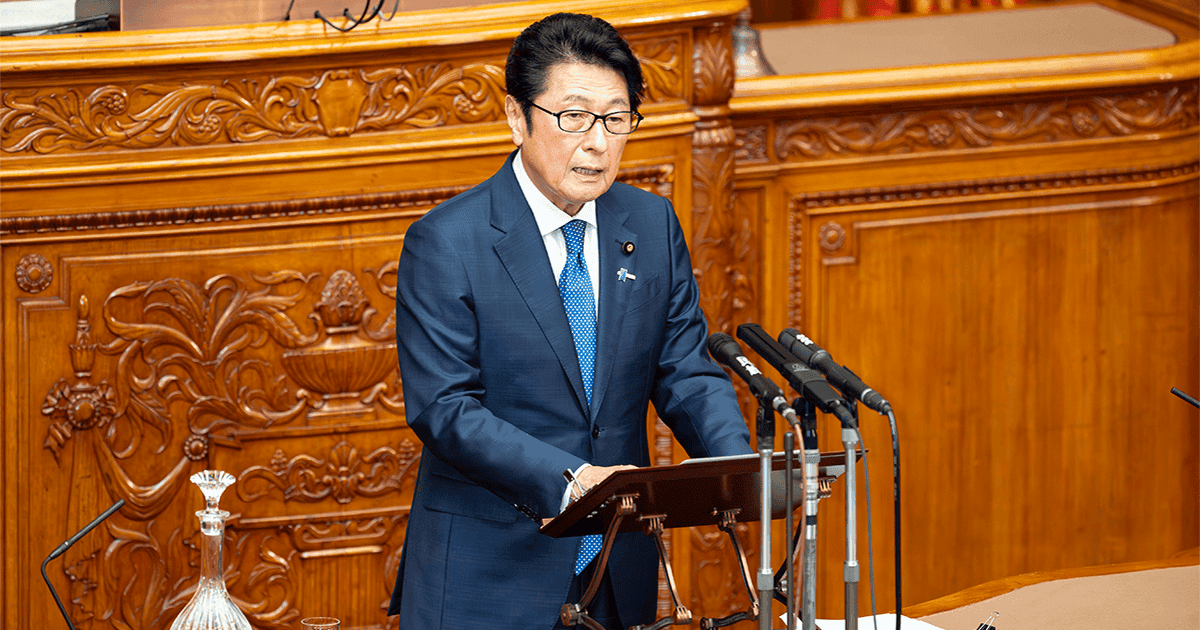
代表質問に臨む松山参議院幹事長
自由民主党の松山 政司です。
会派を代表して、石破新総理の所信表明演説について質問いたします。
冒頭、元日に能登半島を襲った大地震、そして先般の豪雨により、命を失くされた方々に衷心より哀悼の意を表します。また、被害に遭われた皆様方に心からお見舞い申し上げます。
政府には、万全の対応をお願い申し上げたいと存じます。
さて、基本的人権や民主主義を守り、未来に向けて改革を進める自由主義の我々自由民主党の総裁を決める選挙、わが党始まって以来の9名もの候補者が手を挙げ、初挑戦5名、40代2名、女性2名、と多様な候補者が、連日、全国各地で意見を述べ、政策を競いました。
わが党の伝統である自由闊達さと、公正公平さに溢れておりました。
わが国は、外交でも、内政でも、歴史的な転換点とも言うべき、極めて厳しい状況に直面しています。難しい局面であるからこそ、なおさら、多くの知恵が求められます。
今月26日が命日となる参議院自民党幹事長であった吉田博美先生は、23年前、私と同期当選でありましたが、初めてこの世界に入った私に、政治の世界での大先輩でもあり、政治について何かと様々なことを親身になって、ご指導いただいたアニキでもあり、恩師であります。
日頃から、誰にでも、公平に、また丁寧に話を聞いておられました。
そして、常に全員野球をモットーに、現場の先生方を信頼され、しかし責任は自分がとる、こういう方でもありました。
今回の総裁選挙でも、終わればノーサイド、国のため、国民の皆様のために、同じ方向に進むという、わが党の良さを感じるとともに、改めて吉田博美先生のことを思い出しております。
石破総理には、しっかりと、全員野球の精神で、わが党の素晴らしい人材を束ねて、政策を前に進めていただきたいと存じます。
わが参議院自民党も、まさに全員野球をモットーにご指導いただく関口議員会長の下、全力で石破総理・総裁をお支え致します。
そこで、石破総理、まずは、総理として、どのような政治姿勢で、政策を前に進めていくおつもりでしょうか。お伺いいたします。
今から3年前、岸田内閣が発足した令和3年10月は、新型コロナウイルス感染症の第5波が過ぎたばかり。
次の波に備えたワクチン接種や医療体制の整備等の対応が求められておりました。
翌年2月にはロシアがウクライナへの侵略を開始。
力による一方的な現状変更の顕在化に直面するとともに、エネルギーや食料への影響は今なお消えておりません。
アベノミクスの成果によって、経済も雇用も上向きではありましたが、コロナ禍やウクライナ侵略の影響は大きく、デフレからの完全脱却まで、あと少しというところで足踏みを余儀なくされました。
そのような状況の中、岸田総理は 「さまざまな課題に取り組み、結果を出していく」と語り、先送りできない課題に対して、逃げずに真っ向から取り組み、時代を画する成果を上げてきました。
一方、「道半ば」となっているものもあります。
石破総理におかれては、是非とも、岸田政権により大きな方向性が示された課題に対して、スピード感を持って、政策を着実に、前に進めていってほしいと思っております。
そこで、新総理は、岸田内閣の成果をどのように踏まえながら、内外に山積する国難とも言うべき課題に対処し、日本のかじ取りをいかに担っていくお考えでしょうか。お聞かせください。
国民の信頼なくして政治の安定はありません。
政治資金を巡る問題が起きたことについて、国民の皆様に、改めて深くおわびを申し上げます。
真摯に反省し、このようなことを二度と起こさないことで、政治への信頼を取り戻して参ります。
私も、党幹部の一人として、全国の地方議員や党員らと対話する「政治刷新車座対話」で、様々な声に耳を傾けて参りました。
「何をやってるんだ」と、そういった厳しい声を頂きました。
しかし、その声には、国難に立ち向かい、政策を進めていかなければならない、「こんな時こそ自民党、しっかりしてくれ」そういう思いが込められておりました。
「自民党が変わることを示す、最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことだ」
本年8月、岸田総理・総裁は、総裁選に立候補しないことで、自民党トップとして、けじめをつけました。
岸田総理・総裁らしい責任の果たし方でありました。
一方で、自らが率先して進めてきたものには、道筋をつける。
これも前総理・総裁らしい強い責任感の表れでした。
政党交付金の交付停止等の措置、政策活動費の上限の設定や領収書等の公開、そして独立性の確保された第三者機関の設置。
総裁選前、先の国会で成立した改正政治資金規正法で検討事項とされたものについて、しっかりと議論すべきと、党本部の政治刷新本部の下にワーキングチームを立ち上げました。
「自民党は、政治改革を前に進める責任政党でなければならない。」
石破新総理は、この岸田総理・総裁の思いを受け止めて、どのように政治改革に取り組んでいかれるお考えでしょうか、お伺いします。
先月23日、ロシア軍の哨戒機が3度、北海道礼文島付近でわが国領空を侵犯したことに対し、航空自衛隊戦闘機が初めてフレアによる警告を実施しました。
同日、宗谷海峡ではロシア海軍と中国海軍の艦艇合わせて9隻が日本海からオホーツク海に向けて航行したことも確認されています。
数日前には、中国海軍の空母「遼寧」など3隻が日本の接続水域に一時入り、太平洋へ抜けています。
領空侵犯や領海内の航行も、わが国の対応能力を測るべく、少しずつ既成事実を積み重ねていこうとしています。
北朝鮮の弾道ミサイル発射も、核弾頭の搭載能力の向上、防衛網をかいくぐる性能の高度化・高速化、飽和攻撃を可能とする連続・同時発射能力の開発、そして命中精度の改善等を図っているものと思われます。
30年前に米英とともにウクライナと、ウクライナが保有する核兵器の放棄と安全保障に関するブタペスト合意を署名した、そのロシアが、侵略を開始したのです。国連総会決議での完全・無条件撤退要求も聞き入れていません。
残念ながら、「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」という言葉を否定できる状況ではありません。
憲法の前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあります。
制定から80年近くとなる、この理想は、今の日本の現状と大きくかけ離れているのではないでしょうか。
わが党では、9月に開かれた党本部の憲法改正実現本部で、岸田総裁が、「議論を振り出しに戻すようなことはあってはならない。議論だけの時代は終わった。具体的な前進を図っていきたい」と、こう述べて、党としてまとめた論点整理を土台に、改憲に向けた取り組みを加速すべきだと訴えています。
石破総理、世界の、そして、わが国を取り巻く安全保障環境が、これだけ大きく、しかも厳しさを増している中、今の憲法がこのままでよいのか、新たな時代にふさわしいものにすべきではないか、ということを国民の皆様に問いかけ、判断を頂く時ではないかと考えますが、いかがですか。
国と国民の安全と安心、平和と繁栄を踏みにじる蛮行を決して許さない。
その安全保障の最前線であり、同時に最後の砦となるのは、自衛官の皆様です。
わが国を取り巻く脅威が高まる中、自衛隊の装備もそれに応じたものが求められます。
しかし、自衛官の充足率は9割、特に新隊員の採用難は深刻となっています。宇宙・サイバーといった新領域への対応のために組織を拡充しても、人材が確保できなければ、拡大する任務を果たすことはできません。
今なお、自衛隊を違憲とする議論があります。
あらゆる国の組織の中で、存在自体が憲法違反との批判を受けることがあるのは自衛隊だけ。
総理は自衛隊の最高司令官であります。
であるならば、国のため、国民のために、命の危機に直面することも顧みない、厳しい任務に当たる自衛官が、そしてその家族の皆様が、自衛隊や自衛官の存在自体が憲法違反なのかという疑問を微塵も持つことがないようにすべきです。
自衛官の処遇も不十分です。
多くの自衛官の退職は50代半ば、宿舎の老朽化や時代に合った整備の遅れなど職務環境についても課題が指摘されています。
まずは、自衛隊の違憲論に終止符を打つべく、早急に憲法への自衛隊明記のための改正案を国民の皆様にお示しし、判断を仰ぐべきと考えます。
同時に、自衛官の人材確保に向けて、安心して自衛官への道を選べるよう、処遇改善に取り組んでいくことが不可欠です。
これらについて、総理にお伺いいたします。
先月18日、中国、深圳市で、日本人学校の男子児童が男に刺されて幼い命を失いました。謹んで哀悼の誠を捧げます。
6月にも蘇州市で、日本人の母と子が刃物で切り付けられて負傷した事件が発生していましたが、再発を防ぐことはできませんでした。
中国側からは、犯行の事実関係や背景の究明について、何の説明もありません。
中国では、反日機運を煽り立てる言動がインターネットに溢れているとも言われています。このような扇動への対応についても説明が求められます。
中国で、外国人が襲われる事件が続いています。
中国政府への日本単独での要請はもちろん、G7各国と連携した対応も求められます。
そこで、石破総理に、在外での日本人の安全・安心をどう守っていくお考えでしょうか、そして、中国での日本人への襲撃事件の再発防止に向けて、中国政府にどのように働きかけていくのか、ということについてお尋ねします。
北朝鮮による拉致問題は、重大な人権侵害です。
被害者全員の一日も早い帰国を成し遂げるために、北朝鮮に強いメッセージを送るべく、あらゆる場で、拉致問題の解決について、政府や国会が発言して、首脳同士の直接対話実現への後押しをしていかねばなりません。
国際的な世論を更に喚起すべく、NHKの国際放送やインターネットの活用についても拡充を考えなければなりません。
総理は、北朝鮮による拉致被害者の一日も早い全員帰国の実現のために、どのように対応していくお考えでしょうか、お伺いします。
冒頭でも触れた通り、元日に、最大震度7の地震に見舞われた能登半島北部の輪島市などでは、先月、観測史上最大の雨量が記録され、被害が拡大しました。
千年に一度あるかないかと言われるほどの地震に加え、百年に一度の想定を上回る大雨に見舞われた能登半島の方々のお気持ちを思うと胸が痛みます。
被災地からは、「生活再建の最中だったのに、振り出しに戻ってしまった」「度重なる災害で、本当に心が折れてしまう」、こういう多くの声が聞こえます。
石破総理は、総裁選で石川県を訪れた際、地元新聞社の取材に、真っ先に取り組みたい政策は「防災」と迷わず答え、さらに「過疎地で被災したから救われないというのはおかしい」と述べています。
総理は、就任早々、被災地に入られ、被害状況等を自ら確認されましたが、人口減少に直面している地域、そして半島という特性も踏まえ、どのように、能登半島で被災された皆様、そして地域の復旧・復興に当たっていくお考えでしょうか。お伺いします。
日本の国土面積は全世界の0.3%、しかし、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の18.5%が、なんと、わが国で発生しています。
被害総額も世界の17.5%を占めています。
宿命ともいえるわが国の地形・気象条件を直視し、国土強靱化を強力に進めなければなりません。
まずは、令和7年度までとなっている現行の加速化計画の次を、早急に考える時期となっています。
激甚化・頻発化する自然災害に対応した防災・減災・国土強靱化を着実に前に進めなければなりません。
復旧・復興作業に当たる職員の確保や、地域で日頃から建設事業に従事している建設産業の維持・発展も不可欠です。また、安全・衛生・食事・プライバシー等に配慮した避難所の整備も大切です。
南海トラフ地震や首都圏直下地震に備えるために、首都圏一極集中の国土構造を変革し、地方への分散を進めることも喫緊の課題です。
総理、今、政府がやるべきことは、自然災害の脅威から国を守り、国民を守るために、しっかりと予算を確保して、防災・減災・国土強靱化、そして道路や橋、河川管理施設などの老朽化した社会資本の更新を、早急に加速化すること、同時に、高速交通網の整備や活用等による国土構造の変革を思い切って前に進めることだと考えます。ご所見をお伺いします。
新型コロナウイルス感染症、鳥インフルエンザ、エムポックス、これらは同一の病原体により、ヒトと脊椎動物の双方が罹患する人獣共通感染症で、世界では、人の感染症の約6割を占めています。
コロナ禍による健康被害や経済的損失の大きさを考えれば、ヒト、動物、環境の衛生に関わる者が連携して取り組むワンヘルスという枠組みは極めて重要です。
昨年の広島G7サミットに続いて、本年のプーリアサミットの首脳コミュニケでも、ワンヘルスの枠組でのAMR・薬剤耐性に関する記載が盛り込まれました。
わが国でも人獣共通感染症への取組が広がっています。
福岡県では、「ワンヘルス推進基本条例」が制定され、アジア獣医師会連合FAVAの「ワンヘルス福岡オフィスFOF」も開設されました。みやま市では、ワンヘルスセンターの整備が進められています。
感染症対策や環境保全、人と動物の共生社会づくり、そして地方創生のために、アジアの玄関口である福岡県での、この取組を、政府においてもしっかり後押しすべきと考えています。
そこで、わが国における人獣共通感染症対策、そしてワンヘルスに関する取組をどのように進めていくお考えでしょうか。総理にお伺いします。
令和3年10月4日に、発足した岸田政権は、安倍政権、そして菅政権からバトンを受け継ぎ、デフレからの完全脱却に向けて、全力で走って参りました。
2009年当時495兆円であった名目GDPは、昨年593兆円と1.2倍に、本年8月15日に発表されたGDP速報値では、実質で2四半期ぶりにプラスとなる年3.1%増、名目では初の600兆円突破となっています。
設備投資額も、昨年は102兆円と史上最大規模の100兆円超えとなっています。
雇用も、2009年には0.5に届かなかった有効求人倍率は2023年には1.3に、失業率も5.1%から2.6%と大きく改善されました。
今年の春闘では、5%を超える、33年ぶりの高水準の賃上げとなりました。
株価も、本年7月、バブル崩壊後の最高値となる日経平均4万円台を記録。
まさに、30年越しのデフレ経済からの完全脱却まであと少しです。
一方、GDP全体の5割強を占める個人消費は、ウクライナ侵略等を背景にしたエネルギー価格などの上昇による物価高で、設備投資や政府投資など比べると力強さを欠いています。
総裁選直後、為替や株式市場が大きく動いたように、マーケットの疑心暗鬼は避けなければなりません。
まず、財政再建より経済成長が優先されるべき局面であることを明確に示すべきと考えます。
今、優先すべきは、経済成長です。財政再建はその先にあります。
財政出動に躊躇すべき時ではありません。
本年4月・6月期の日本経済の需要と供給の差を表す「需給ギャップ」は年換算で4兆円程度の需要不足です。
貯蓄から投資への流れを変える必要もありません。
何としてでも経済再生、そのためには、まずは物価高に負けない賃上げの流れを確実なものにし、岸田総理が進めてきた「新しい資本主義」を加速させなければならないと考えます。
石破総理のお考えと今後の具体的な方針をお聞かせください。
この10月から児童手当が拡充されました。
所得制限は撤廃、支給期間は「高校生の年代まで」に延長、そして、第3子以降には月3万円が支給されます。
来月からは、家計が苦しいひとり親世帯などに支給する児童扶養手当も拡充されます。
私は、安倍内閣で少子化対策担当大臣を務めた際、関係者の理解を得ながら、保育所の充実等のために「子ども・子育て支援法改正案」を成立させていただきましたが、平成29年当時に2万6千人だった待機児童は昨年2千7百人となっています。
当時は後ろ向きの声もありましたが、信念を持って政策の旗を振ることで、理解を広げた結果であると思っております。
今回の総裁選では、自民党の政策力を改めて実感できるほど、候補者の多くの方々から様々な少子化対策が提案されました。
非正規雇用の問題への対応や働き方改革の一層の推進を図り、若い世代の中長期の安心や希望を高め、不本意未婚を解消する、あるいは、全国どこで子育てしても給食費・医療費・教育費を無償化する、などがありました。
総理自身が先頭に立って、多士済々の方々の政策をまとめ上げ、少子化克服の旗を振りあげれば、必ずや、少子化の波をくい止め、逆転させる流れが生まれてくるものと信じております。
石破総理、今回の総裁選での議論も踏まえ、どのように少子化、こども・子育て政策の充実、強化を進めていくお考えでしょうか。お伺いいたします。
今から35年前、ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終結しました。
各国が相互依存関係で結ばれ、その成長の果実を享受し合う時代がやってくるとの期待が広がりました。
しかし、現実には、中国が著しい経済成長を活かし、軍事力、外交力を増強しています。
権威主義国家が台頭し、世界のパワーバランスは大きく変化、分断と不安定化が広がり、力による一方的な現状変更への脅威が深まっています。
本年11月には、米国大統領選挙が行われます。
東アジア、さらにはインド太平洋地域の平和と安定のためには、新たに就任する米国大統領が、この地域に高い関与の意思を示すことが極めて重要です。
石破総理は、政権交代以降、再構築し、深めてきた米国大統領との信頼と盟友関係を、新大統領との間でも一層発展させていかねばならないと思います。
新大統領が決まればすぐに米国に飛び、同盟国の総理として、胸襟を開いて会談できる関係の構築に努めて欲しいと思います。
同時に、わが国の強みは、分裂や混乱ではなく、揺るぎない、そして多くの国が共有する価値観に裏打ちされた外交です。
本年7月に第10回太平洋・島サミットが開催されましたが、私は、その準備のため、総理特使としてバヌアツを訪問しました。
その際、先方政府からは、岸田総理、そして日本による「自由で開かれた国際秩序」の構築や気候変動等に果たす役割の大きさへの評価、そして期待が述べられました。
安倍政権において掲げられた「自由で開かれたインド太平洋」が、太平洋・島サミットという枠組みを通じて、国際秩序を乱す中国を抑止していく概念として、国際社会に浸透し、定着していることを実感いたしました。
そして、このほか、日米韓や日米豪印4か国の「クアッド」、日ASEANなど、これまで積み上げてきた外交・安全保障の枠組みもあります。
そこで、日米同盟、そして、自由、民主主義、人権、法の支配という価値観を共有している国々との連携の強化との関連性を踏まえ、どのようにわが国の外交を進めていくお考えでしょうか。総理にお伺いします。
参議院は創設以来、選挙区選挙では都道府県ごとに参議院議員を選出してきました。
しかし、東京への人口一極集中と地方からの人口流出が進み、一票の較差が拡大し、やむなく、平成28年以降、合区選挙区が導入されました。
わが党は、合区選挙区を解消し、各都道府県から通常選挙ごとに少なくとも一人の参議院議員を選ぶことができるように憲法改正を訴えてきましたが、実現できておりません。
石破総理の郷里である鳥取県と島根県、徳島県と高知県という合区選挙区となった県では、参議院選挙の投票率が急落したほか、無効票も多数発生しています。
合区選挙区の弊害への認識は、徐々に広がっています。
昨年の最高裁判決では、「有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えていることがうかがわれる」と、こう示されております。
私が座長を務める「参議院改革協議会」の下に設置され、全ての会派からなる「選挙制度専門委員会」では、合区の弊害は共通認識として、解消すべきとする意見が大勢を占めました。
参議院の在り方を踏まえて、更に議論を深めて参りたいと思います。
投票価値の平等は大切です。
しかし、人口という数字だけで選挙制度を決め、有権者を投票から遠ざけるようなことがあれば、民主主義の根幹を揺るがしかねません。
衆議院選挙でも、人口増加が著しい大都市部で、選挙ごとに選挙区割りが変わり、国民と議員の関係の希薄化を懸念する声もあります。
経済も教育もなにもかも集中している大都市が、地方で生まれ育った人を吸収していくことで、議員定数が益々増え、政治力が更に強まります。
一方、人口減少に苦しむ地方は、その声を届ける議員も少なくなってまいります。
地方創生をライフワークとされている石破総理にお伺いします。
人口減少に苦しみ、社会サービスを維持する力も失われつつある地域から、その声を届ける議員がいなくなる選挙制度を、どうお考えですか。人口減少に苦しむ地方にとって、政治の光はどうあるべきとお考えでしょうか。お伺いします。
「着々寸進 洋々万里」
石破総理のお好きな言葉と伺いました。
一歩ずつ事を成せば、万里の海の彼方にも到達できる。
参議院自民党も、石破新総理と、その思いを共にして、この国を守り、国民を守り、そして大切な故郷を守り、そして未来を守るため、政治を前に進めていくことを申し述べて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。






















