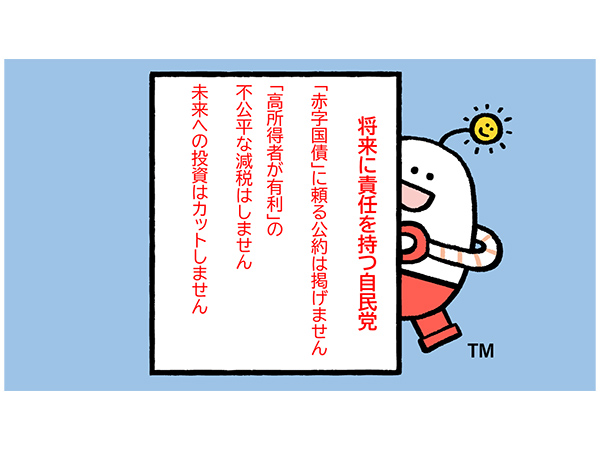地域福利増進事業で備蓄倉庫(左上)や蓄電池設備等の災害関連施設のほか、太陽光発電設備(右下)や小水力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備も整備可能になります。
政府は2月4日、所有者不明土地法改正案を閣議決定しました。いわゆる所有者不明土地とは不動産登記簿等により直ちに所有者が判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地。所有者の探索には膨大な時間とコストがかかるため、公共事業や土地の民間取引で重大な支障をきたしています。民間団体が取りまとめた調査結果では、平成28年時点の所有者不明土地総面積は九州本島を上回る410万ヘクタールに上り、必要な対策が講じられなければ、令和22年には北海道本島に迫る720万ヘクタールに増加する可能性が指摘されています。所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」は喫緊の課題です。
災害関連施設と再エネ発電設備の整備可能に
改正案では所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害関連施設や地域住民等の福祉・利便の増進に資するものとして一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業を追加します。現行の対象事業は公園、広場、駐車場、購買施設、公民館、仮設道路等の整備に関する事業ですが、激甚化・頻発化する自然災害に対応するための施設としての利用ニーズに応えます。
民間事業者が購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を整備する場合、土地使用権を現行の10年から20年に延長します。「現行の10年間では施設を整備しても費用を回収できない」といった指摘が出ていました。事業対象の土地が所有者不明土地であるか、事業内容等に反対する権利者がいないかを確認するための、事業計画書等の縦覧期間を現行の6カ月から2カ月に短縮し、事業スピードの加速化を図ります。不明所有者等のために民間事業者が供託する補償金は、都道府県知事が定める支払時期までに分割で供託することを可能にします。供託金を毎年分割で供託しながら、所有者不明土地で対象事業を行うケースも想定されます。
また、事業対象の土地に朽廃した空き家や工場の建屋等の建築物がある所有者不明土地を追加します。

地域福利増進事業等の対象土地に、損傷・腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないことが確実だと見込まれる建築物がある所有者不明土地を追加します。現行は更地か補償金の算定が容易な物置等がある所有者不明土地に限定しています。