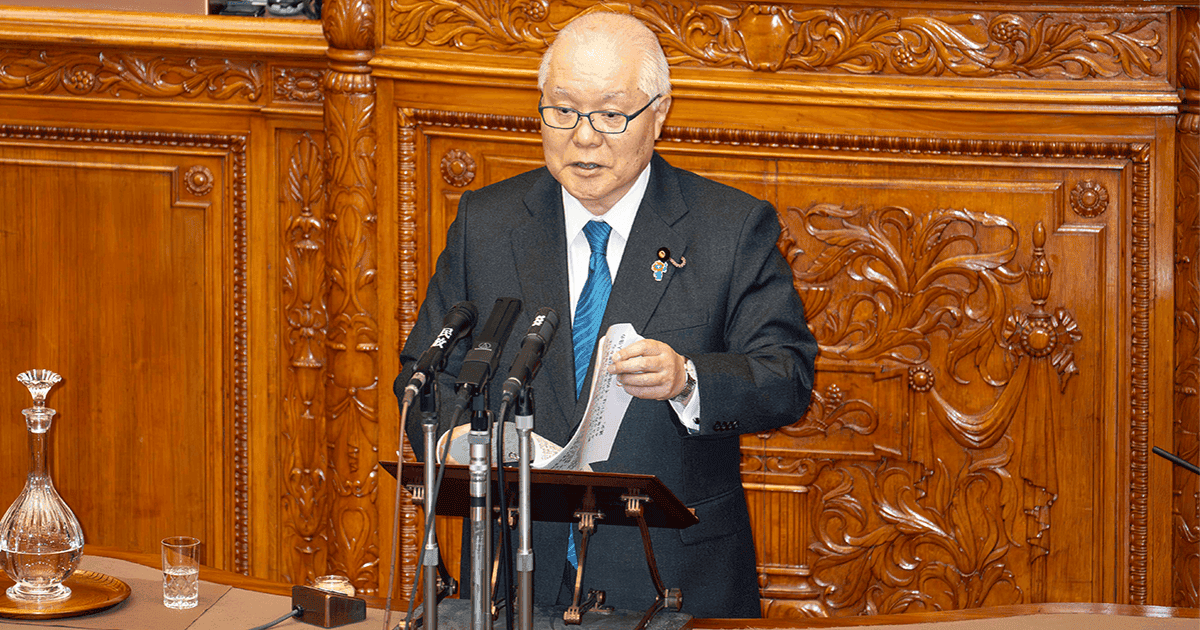
代表質問を行う武見敬三参議院議員会長
自由民主党の武見敬三です。
私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説をはじめとする政府四演説について質問いたします。
現在、国内外において、地政学的な対立が激化する中、「自由」、「民主主義」という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。
そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は、人口動態の変化です。
我が国の総人口は2020年の約1億2615万人から2065年には9159万人まで減少します。
15歳から64歳人口、いわゆる生産年齢人口は、2020年代の10年間では433万人が、さらに2030年から40年までには、その倍の860万人強の減少、つまり、その頃の東京都の生産年齢人口に匹敵する人口が消滅することとなります。
昨年の出生数は68万人台、ピークであった1949年の270万人弱と比較すれば実に四分の一。人口減少は不可逆です。
昨年、団塊の世代がすべて後期高齢者になりましたが、平均寿命の延伸により10年後にはかなりの方々が85歳以上となります。独居老人も増加し続けその7、8割を女性が占めます。認知症の患者も増える超超高齢社会が到来します。
東京など都市部では高齢者人口は増え続け、地方では減少し続けます。
都市部、特に東京も相当深刻、かつ極めて困難な高齢化問題に直面します。
人手不足はますます深刻化します。超高齢化社会が進展し、担い手が減れば、稼ぐ人も減り、消費する人も減ります。
その間、貧富の格差が拡大するとともに、SNSの投票行動に与えるインパクトも増大し、国民世論は左右両極に分化、中道勢力が縮小していくことで、政治の不安定化が構造化することが予見されます。
2030年代の危機は、機能不全となりがちな民主主義と相まって、極めて深刻なものになると危惧されます。
これを放置すれば、我が国は衰退するのみです。
私は、昨秋まで1年1か月、厚生労働大臣を務めさせていただきました。また、我が国の保健・医療・介護の価値と可能性を誰よりも信じ、ライフワークとして取り組んでまいりました。そして、デジタル化とデータサイエンスに基づく「未来思考」を旨としてまいりました。
その立場から、死中に活を見出すのは、まさに今であり、「過去の延長線にある政策だけでは日本の未来はない、創造的な未来こそ求めなければ活路は見つからない」ということを申し上げたいと思います。
2030年前後から深刻化するこうした事態を解決する未来志向のビジョンと、それを実現する体制を創り上げること、これこそが、今、必要なものなのです。
私は本日、こうした問題意識の下、質問してまいります。
人口が減れば国内需要が減る。そうすれば経済規模は縮小し、国力は衰退する。デフレ・スパイラルから抜け出せなくなります。
すぐにでも、グローバルな視点から、他国との比較優位がある分野、特に保健・医療・介護のように国内需要のみを対象としてきた分野では、医学・医療の進歩を吸収し、持続可能性を高めるため、国内で制度改革を実践する際に、産業政策を導入し、国内外に新たな市場を開拓していかなければなりません。
そして、国民皆保険制度として築き上げてきたユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)、つまり全ての人が経済的困難を伴わずに、適切な予防や治療、リハビリ等の保健医療サービスを受けられる環境は、明らかに我が国の強みであります。
我が国は、UHCについて、国連の持続可能な開発目標(SDGs)への位置付け、G7伊勢志摩サミット、G20大阪サミットでの安倍元総理、G7広島サミットでの岸田前総理のほか、国連総会、WHO等様々な国際的なフォーラムでその重要性を訴える等、リーダーシップを取ってきました。
そして、近未来において急速に高齢化が進み、日本に後れて我が国が直面している課題への対応に迫られるアジア・インド太平洋地域に、日本のソフトパワーの一つとして、UHCにより解決策を提示していくことは、有望な産業政策となります。
そこで、アジア・インド太平洋地域における医療水準の向上や健康格差の是正に貢献するとともに、インバウンド、アウトバウンド等において我が国の産業政策を推進していく上で重要な人材となることが期待される外国医療人材の育成事業として、我が国医学部への海外留学生のための奨学金制度の導入など、医学部定員数の削減と併せて海外留学生の受け入れ体制を整備してはどうかと考えます。この点について、総理のご所見をお聞かせください。
併せて、途上国における保健財政の拡大とその適正な配分により、持続可能性の高いUHCを達成するためには、保健財政担当者のための人材育成を行うことが重要です。
そのため、我が国は、WHO及び世界銀行と協力し、人材育成の世界的な拠点となる「UHCナレッジハブ」の日本設置を進めていますが、「UHCナレッジハブ」等の外交的貢献を進めつつ、保健・医療・介護分野を産業政策の対象として、UHCをどのように我が国の成長戦略に位置付けていくのか、総理のご見解を伺います。
我が国では、欧米で承認されているが日本では承認されていない未承認薬は140品目ほどあり、こうしたコストのかかる医学・医療の進歩の果実が国民に届かないという実情があります。このうち、6割程度は、そもそも日本での開発に着手されておらず、ドラッグラグ・ドラッグロスが発生しており、我が国の医療が先進国としての水準を保てなくなる兆候も出始めています。
医学・医療の進歩を我が国の医療保険制度にどのようにして取り込むのか。
その解決策の一つが、保健・医療・介護分野の産業政策として、我が国への医療インバウンド戦略を積極的に進めることです。
医療滞在ビザの発給件数は、2022年1804件、2023年2295件と増加傾向にあります。短期滞在ビザ等で我が国の医療を目的として訪日されている方々も含めれば、医療インバウンドは推計で2万人から3万人程です。
訪日外国人には我が国の健康保険が適用されず、各医療機関が自由診療として任意に価格を設定することとなります。
医療インバウンドの拡大は、我が国の有力な成長戦略分野、日本の稼ぐ力として極めて有望であります。
同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民すべてが医学・医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。
そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学・医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも、自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理のご認識を伺います。
また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために、医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考えますが、厚生労働大臣のご所見を伺います。
もう一つの成長のカギは、創薬力です。
日本はかつて低分子医薬の分野で世界市場の1割弱を占めていましたが、現在の主流であるバイオ医薬品開発に出遅れ、医薬品の貿易収支も、2000年代になると赤字額が急増し、一昨年は、日本の貿易赤字の三分の一強を占めています。
一方で、ライフサイエンスにおけるアカデミア、研究領域での日本の比較優位はいまだに高いものがあります。研究分野での日本の存在感が保たれている今こそ、我が国の創薬分野におけるイノベーションを加速させなければなりません。
私は、厚生労働大臣として、多様なイノベーション、最新技術を医療現場で活用するとともに、産業政策の観点も踏まえたスタートアップ支援の観点からも創薬力の強化を推し進めてきました。
また、政策を実行する体制として、グローバルな創薬に携わっている海外の人材を国内に直接活用するスキームがなかったことから、創薬に関わる主要先進国の研究者と結びつけ、創薬の基盤を強化し、支援する仕組み、つまり、グローバルな創薬エコシステムと連結する研究開発の創薬基盤の再構築と、そこから起業家と結びつけるスタートアップ支援を間断なく行う組織の立ち上げも打ち出しました。
海外で創薬に携わる極めてレベルの高い専門家と我が国の創薬研究者が組むことで研究開発能力はダイナミックに高まっていくことが期待できます。
そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結びついた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理にご見解を伺います。
政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。
ポストコロナの政策を考えるにあたっても、今一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。
我が国には、健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回りました。
昨年8月、厚生労働省が取りまとめた「近未来健康活躍社会戦略」には、電子カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの構築、医療等情報の一次利用及び二次利用の推進など、医療現場の生産性向上と健康活躍社会の構築という二兎を得るための医療DXの推進方針を盛り込みました。
これを受けて、政府は、現在の社会保険診療報酬支払基金を改組し、医療情報プラットフォームの実行主体として、位置付ける予定です。
しかし、関係するシステムを統合する際に、単に組織を足し算するだけでは、一体的に機能できるとは限りません。また、組織自体のガバナンスが保たれるわけでもありません。
医療DXのさらなる推進による患者自身の治療、そして公的医療保険財政への貢献、併せて、医療DX活用の前提となるマイナ保険証の一層の利用促進を、どのように進めていかれるのでしょうか。
さらに、医療DX推進のために新たに改組される組織のガバナンス強化の方針をどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣に伺います。
我が国の近未来を考えるには、都市と地方の高齢化の過去、現在、未来を踏まえることが不可欠です。
過去における高齢化は地方が中心でしたが、地域社会の支え合いの機能があり、家族のサポートも期待できた時代の問題でした。
近未来では、地方の高齢者人口も減少します。
片や、これから都市部では、異次元の高齢化が進展します。
75歳以上、それから85歳以上の超高齢化社会が出現し、2040年まで増加し続けます。都市部における超高齢化は地域社会の支え合いや家族のサポートが希薄化していく中で進展します。高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。
都市部と地方で、高齢人口の増減が著しく異なることから、2040年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市部と地方で保健医療介護の需要と供給のバランスの違いを全体としてとらえ、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。但し、中長期的に、今まで以上に医療にお金がかかる様になる事だけは明白です。
現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。
都市と地方で保健医療介護の需要と供給のバランスの違いを全体としてとらえたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。
そこで、当面の問題と近未来の課題を一体的に考えて、地方創生とも連動した近未来の保健医療介護のグランドデザインをいかに設計したら良いのか、同時に、物価高及び経済成長等による税収の増加部分から新しい医療財源を確保する仕組みをつくることが重要と考えますが、総理のご所見をお伺いします。
外交・安全保障に目を転じます。
政治目的を達成する為に軍事力を行使する非民主的な権威主義体制が、その軍事力に裏打ちされた勢力範囲の拡大を着実に実行しようとする危険な国際情勢となり始めています。
特に、我が国の周辺には、冷戦の残滓とも言える分断国家が朝鮮半島及び台湾海峡に存在し、紛争が起きる軍事的リスクは年々増大しています。
この増大する軍事的リスクに対応して、我が国の自由と民主主義を基本的価値とする独立した主権国家としての立場を堅持する為に、平和主義に基づき近隣諸国と協調し共存する外交的努力に務めつつも、同時に我が国の安全保障三文書に基づく「戦略的能力」の強化は必須であります。
しかし、「戦略的能力」の強化を語るにおいても、地政学的な対立が深まる中、従来のような「戦争か平和か」との二分論は、あまりにも非現実的であり、現実的な国家戦略を語れません。
何が「戦略的意志」で、何が「戦略的能力」なのかを明確に意識して国家戦略を構築していくことが極めて重要となります。
我が国の「戦略的意志」とは何か。
それは、戦後貫かれてきた「平和主義」であります。
我が国の「戦略的能力」とは何か。
それは、我が国の防衛力と日米同盟を基軸とした同志国を含めた戦略的連携に裏打ちされた「抑止力」であります。
この「戦略的意志」と「戦略的能力」を如何にそれぞれ具体化していくのか。これが我が国の国家戦略となります。
「戦略的意志」と「戦略的能力」、それぞれの具体化は極めて現実的な対応として必要です。
「戦略的意志」である平和主義を国民の意識の中でしっかりと定着させるためには、人間の安全保障と言った未来志向でさらに具体的な政策概念により、人類社会と地球とを共存させることを前提に、人道上の課題や保健医療介護といった国境を超えた共通課題に平素から常に積極的に貢献する積極的平和主義が何よりも重要であると考えます。
その際、我が国は保健医療介護の分野において国際社会で顕著な比較優位性があることを踏まえ、例えば、休戦が一時的に成立しているとはいえ人道上の課題に直面しているガザ地区の人々の健康回復のため medical evacuation を含め保健医療の支援を積極的に実施していくことが考えられます。
このように、変化する安全保障環境の中、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで、平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないように、より確実に抑止することになる、と考えますが、総理のご見解をお伺いします。
戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも、抑止力を完結する為には「自らの身を自ら守る」という覚悟が必要と考えます。
世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、「自らの身を自らが守る」という覚悟なくして抑止力は完結せず自国の安全を守ることはできません。
その上で、国民の多くが自衛隊員に対して感謝の気持ちを持ち、その名誉を守ろうとすることなくして、将来も永続して隊員の募集を行うことは困難になると考えます。
また、自らの意思で、国家、国民のために、身をもって責務の完遂に務め、国民の負託にこたえる覚悟を持つ人材の育成も極めて大切です。
そのために、何をしたら良いのか、総理のご所見をお伺いします。
そして、その際、現在の日本国憲法についても考える必要があります。
「戦略的意志」と「戦略的能力」という観点からみると、憲法第9条は、「戦略的意志」としての平和主義を第1項に、「戦略的能力」については2項に示しています。
あらゆる脅威から我が国の主権を守り、国民の生命を守るため真に必要な防衛力を確保するが、抑止力として、いかなる防衛力を保有しても、紛争を解決する手段として武力の行使をすることはないという平和主義に基づく現実主義は貫かれるべきです。
同時に、自衛隊、自衛官が違憲論にさらされることに終止符を打つべきです。そこで、現行の9条1項、2項は変えず、第9条の2を加えるといった我が党の条文イメージを含め、憲法改正について、今こそ議論を前に進めるべきと考えますが、総理のご所見をお聞かせください。
今月20日に就任したトランプ米国大統領は、第一次政権時より、大統領個人の影響力を圧倒的に強化しています。
就任演説で「常識の革命」を始めるとして、「領土の拡大」という言葉も予測不能です。
基本的には、現実主義者であり、ディールを重んじる大統領とも言われています。
今回の就任式に出席した岩屋外務大臣は、ルビオ国務長官と会談し、日米同盟のさらなる強化に向けて緊密に連携していく方針で一致したほか、日米とオーストラリア、インドの4か国の枠組み「クアッド」の外相会合では「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、重層的な連携を行うことを確認しました。
これら戦略の共有を首脳同士でしっかりと確認することが極めて重要となります。
日米の首脳同士の信頼関係が、この抑止力の維持強化に今まで以上に重要になったと考えます。
そこで、日米両国が、自由で開かれたインド・太平洋、そしてクアッドを戦略的に共有していることを、早急に首脳会談にて、米大統領と確認した上で、日米同盟に基づく更なる抑止力の強化を図ることが最重要と考えますが、石破総理のご所見をお伺いします。
今月20日に就任したトランプ米国大統領は、就任早々、温室効果ガス削減を定めたパリ協定やWHO・世界保健機関等の国際的枠組みからの離脱に関する大統領令に署名しました。
米国は国際社会共通の課題の解決から距離を置こうとしており、第一次トランプ政権時のWHO離脱でみられたマルチ外交での孤立主義と、それによる外交的な真空地帯が再び発生しようとしています。
一方、我が国は本年11月に世界銀行及びWHOと連携して立ち上げる保健財政の研修プログラムを中心としたUHCナレッジハブのような、医療・介護分野など日本が得意とする分野での貢献により、米国の撤退により生み出されたマルチ外交における真空地帯を埋め合わせ、その分野での課題解決につながる保健外交を実施することで、平和主義に基づくマルチ外交における我が国の影響力の基盤を強化することができます。
米国の国際的な枠組みからの離脱と、それにより生まれるマルチ外交の真空地帯を埋め合わせるために、我が国の平和主義に基づくマルチ外交をこの際、積極的に展開することで、日本の貢献を通じて、我が国国民が平和主義に確信と自信を深めることにつながると考えますが、総理のご所見をお聞かせください。
私は、厚労大臣在任当時、北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記等と面会し、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。
改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感しました。また、保健分野はじめ中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じています。
日中間に様々な課題が横たわる中だからこそ、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図を創り上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないとのメッセージを「同盟国」、「同志国」と連携しながら発し続けること、高齢化、社会格差、環境・保健分野等での共通課題解決に、国境を越えて積極的に連携していくことが求められると考えます。
その点で、先々週、6年3か月ぶりとなる中国共産党との政党間交流「日中与党交流協議会」等に臨むための与党幹事長の訪中、また、昨年12月の外務大臣の訪中といった政府や党などによる重層的な交流や対話は極めて有意義であったと考えます。
その上で、やはり、首脳同士の信頼関係の構築が極めて重要です。
中国との間に共通利害を見出し、共に解決していく前向きな外交関係の構築に向けた重層的な外交の重要性への認識をお尋ねした上で、日中首脳会談の早期開催の決意について、総理にお伺いいたします。
最新の自殺対策白書によると、令和5年の自殺者数は前年からやや減少しましたが、小中高生の自殺は増加しつつ、過去最多だった前年と同水準で推移しています。自殺や不登校などにつながるいじめの件数も過去最多となっています。
現在、政府は、自殺やいじめの要因の分析や自殺予防のためのチームの設置などに取り組んでおりますが、厚労省、文科省、こども家庭庁等の関連する府省庁がしっかりと連携をして、多方面から対策を講ずる体制を創り上げることが大切です。
昨年末、超党派の議連で石破総理に、自殺防止対策の強化を申し入れましたが、子どもの自殺防止に向けた取組についてご所見をお伺いします。
最後となりましたが、政治資金に関わる不記載により、政治への信頼と期待を大きく損ねることとなったことを、深く反省し、我が党の信頼回復につながる、わかりやすく、そして誰もが納得のできる政治改革を必ずや成し遂げて参りたいと存じます。
その上で、昨年を振り返れば、我が国をはじめ、民主主義国家の政権与党には、インフレなどを背景に政権への不満が噴出し、国民世論が左右両極に分裂し、中道勢力が後退し、政治の不安定化が構造化する厳しい結果となりました。また、世界における議会制民主主義のあり方が問われた年でもありました。
ポピュリズムの台頭に加え、SNSによる偽情報の拡散や外部からの選挙介入等もあり、民主主義の機能を損ない混乱を深めています。
余波は、我が国にも及びつつあります。
兵庫県知事の出直し選挙やその前後の混乱等の間に、SNSによる誹謗中傷やデマが広がりました。また、尊い命が失われる事態ともなりました。
昨今のSNSの政治に及ぼすインパクトに鑑みれば、人権を侵害したり、民主主義をゆがめたりすることがないよう、法律的にも厳しく規制していくことへの必要性について議論すべき時と考えますが、総理のご認識をお伺いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。






















