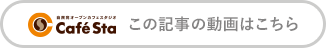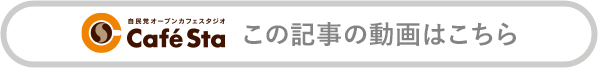主な活動:各界各層との交流
CafeSta文化・スポーツイズム!
2016.02.19
収録日時:平成28年1月27日
初回のゲストは服部栄養専門学校の服部幸應さん。二之湯武史青年局文化・スポーツ部長との間で、料理に目覚めた幼少期や料理学校を作ったきっかけ、和食ブーム、若者へのメッセージなど、多岐にわたって語り合いました。
- 服部
- 2歳で包丁を持ち、小4からひとりで料理を作っていました
- 二之湯
- 皆さん、こんにちは。自民党青年局の文化・スポーツ部長を務めております二之湯武史と申します。今日から新しいCafeStaの番組ができまして、その名も『スポーツ・文化イズム!』というタイトルです。これから主に文化界、スポーツ界で活躍をされている一線の方々をゲストでお呼びをして、今まであまり自民党にご縁がなかったような分野の方を中心にお話を聞いて、特に青年世代の皆さんが活躍するために、そういう皆さま方がどんな青年期を送っておられたのかというようなお話をお聞きする、そんな番組にしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
今日は1回目で、ゲストに服部専門学校でおなじみの服部幸應先生に来ていただいております。では服部先生、よろしくお願いします。
- 会場
- (拍手)
- 服部
- 失礼します。こんにちは。
- 二之湯
- よろしくお願いします。
- 服部
- よろしく、どうぞ。
- 二之湯
- 服部先生とは、私が国会議員になってからですけれども、私が立ち上げた日本食文化普及推進議員連盟という議員連盟でご縁を頂いて、それから非常にいろいろとご指導いただいている、そんな関係でございます。
早速なんですけど、先生はこの料理の世界に入られたのは何歳ぐらいからですか。
- 服部
- 家が料理を教えている家だったこともあるので、おばあちゃん子なんです。僕が気付いたのは4歳ごろに包丁持ってたんだけど、覚えがないんですけどおばあちゃんに言わせると2歳から持たせてたというんです。そんなような中で育ったのかもしれません。
- 二之湯
- もともと服部流というかそういう流派の。
- 服部
- そうです。流派みたいのがありまして、そういったものを父親が引き受けて、母親がまたそれを受けてというような流れはあったんです。僕は好き勝手に料理をあちらで食べてこちらで食べてとまず食べて、そしておばあちゃんの言われるように包丁を使って料理を作るのが面白くて、そんなことで育った人間です。
- 二之湯
- なるほど。私も世にいう2世議員でありまして。選挙区は父親とは違うんですけども、小さいころからおやじがこの世界におりましたので、何かもう政治家が何なんやと思って、どちらかというと反発が強かったんです。先生の場合はそういうおうちに生まれて。
- 服部
- 反発しないんですかって、よく聞かれるんですよね。素直でしなかったんですよ(笑)。いや、しなかったというより、何をしていいか、何となく周りが食に満ちあふれてたというか、そういう中で育ちましたんで何か自然にその道に入ってしまったんです。
- 二之湯
- なるほど。じゃあ他の選択肢とかもう全然考えなかったという感じですか。
- 服部
- 気が付いたらやってたという感じです。だって小学校4年のときに、料理ちょっとおまえも作れと、日曜日の昼飯から作れよと、前の土曜日から言われるわけです。
- 二之湯
- それは家の。
- 服部
- そう、うちの父の。まず天丼作れとか言うんですよ。
そうすると、米といでエビを手に入れて、そして衣をつけて揚げて、どんなあんばいで丼つゆを作るかとか、そういうのをやるわけです。最初出したら一口食べて、まずいって言われました。そして「おまえ、こんなの料理じゃない」と言われて。確かに子どものときからいろんな、米の炊き方とかやってたんです。だけど総合的に、丼という一つの形を作り上げるということに関しては初めてやったわけですよ。それは母がやってたりおばあちゃんがやってたやつを組み合わせてやるということはあったけど、全部を一人で最初から最後まで、もう誰も手伝ってくれないんです。
- 二之湯
- それは幾つのときですか。
- 服部
- それが小学校4年です。料理はそれまでいろいろやってたけど、一人で作るのは小学校4年。
- 二之湯
- すごいですね。小学校4年で天ぷら揚げたんですか。
- 服部
- 揚げました。もちろんそれまで揚げてたし、だけど組み合わせて一つの料理にしなくてはいけないという意味からいうと。それでまず、まずいって言われた。そしたらおばあちゃんが「おまえかわいそうにね、じゃあ食べに連れていってあげる」って、食べ歩きを小学校4年からやった(笑)。
それで、近所のおそば屋さんの天ぷらだとか、本当に高級な天ぷら屋に行って、そこで天丼を頼んでみて。そしたら、ある神田のほうにある店に実は行って食べたときに、おいしかったんで。そしたらおばあちゃんが「この丼つゆの作り方を教わろうや」と言って。子どもだから、小学校4年に対してはそこのご主人も素直に教えてくれたのね。
- 二之湯
- 警戒せずに。
- 服部
- 警戒せずに(笑)。それを教わって、それで料理を作ったらうまくいったんですよ。そしたら、うまいって言われたんです。うまいって聞いたら、もうこれからうまいって言わせようと思って、目標ができたんですよ。
- 二之湯
- じゃあ、やっぱりその4年生の原体験、それがやっぱりいまだに頭にびっしりとこびりついてるわけですよね。
- 服部
- そうですね。
- 二之湯
- 今、さっきちょっとコメントで、2世には2世の悩みがあるんだなみたいのが出てたんですけども。そういう意味では、4年生ということはほぼ10歳ですよね、その時期にもう天ぷら揚げて天丼のだし作って、そこからはもうじゃあ当然、さらに進化していったわけですよね。
- 服部
- 当然そうなるんですけども、実は後からこれは分かったことですけど、要は幼児期に覚えたものというのは、後の大人になって覚えるよりも全然伸びがあるんですよね。どのくらいあるかというと、大人の6倍吸収率があるんです。もしオリンピックで金、銀、銅を取らせたかったら、子どもは幼児期に運動しなければ駄目。もしピアノだとかバイオリンを教えたければ、マエストロにするにはやっぱり幼児期なんです。
語学も、確か2〜3週間前でしたけど、大学の英語検定に受かった子がいるんです。幼稚園の子が受かったんです。そしてそんなのは異例で、大学生だって落ちるわけですよ。いつからやってたの? って言ったら、子どものときに両親が英語の漫画のビデオを与えたんだそうです。それを子どもたちが観ているうちに、そのしゃべってる姿を兄弟がそのまままねしたらしゃべれるようになってしまった。あまりぺらぺらしゃべるもんで親は何言ってるか分からないと。親は全然英語が分かんないわけです。それで検定に出したんです。そしたら1級受かってしまった。
だから幼児期って意外と大事なんで、そのころに刷り込み、インプリンティングというのはやっぱり大事なのかなと思いますね。


- 二之湯
- 昨日、奥さんがおひたしを作ってくれました
- 二之湯
- 今、いいお話を頂きました。今、私も、幼児教育振興基本法という法律を作るメンバーでもあるんです。日本の教育というのは、小学校、中学校という義務教育は国際的にもものすごく評価が高いんですけども、予算的にもそうなんですが、実は弱いのが幼児教育と高等教育なんです。高等教育、つまり大学ですけれども、これもさっきからコメントが出てますが、親の収入格差、経済環境によって学歴格差もつきつつあると。
ここはわれわれも非常に問題意識を持っていて。今、文科省も含めて、そういう思いを持ってるんですけども、就学前教育というのも、おっしゃったように三つ子の魂百までということわざがあるように、実はわれわれが思っている以上に決定的な要因になり得る時期なんじゃないかと。
- 服部
- そうですね。
- 二之湯
- そして、今そういった幼児期のさまざまな教育の追跡調査のデータなんかが、30年、40年かけて出てきたようなものが徐々に出始めてるんです。今、先生がおっしゃったように、学力もそうなんですが、特に感性とか、つまり数字で評価できない、粘り強さだとか思いやる心とか、そういうようなものが非常に、就学前幼児期教育は重要だということは、もう最新の研究でも明らかになっています。今の先生のお話というのは、改めてそういうのを裏付ける話だと思うんです。
- 服部
- もう亡くなられたんですけど国語検定の石井先生という先生が、日本は漢字を小学校から教えると言うんです。1年生から6年生までトータルで教えて最後に試験をやった場合、平均点が57点ぐらいになるらしいんです。ところが幼児期にその6年分の漢字を教えてしまうわけです。そうすると何と試験が94点。もうはっきり言って幼児期に教えてしまったほうが全然吸収率高いんですよ。それを何か日本は見過ごしてるような気がする。
- 二之湯
- やっぱりそういう、常識的なものがもう完全に固定化してしまって、人間の本来の顕在化してない能力というのが実はもっとあるんじゃないかと。脳は実は3パーセントぐらいしか使ってないみたいな話もありますから。
それではさっきの先生の幼少期の話に戻りますけれども。じゃあ中学、高校というような時期というのは、もう全く疑問を持たずにその世界にずっと進まれたわけですか。
- 服部
- たまに料理をやらなくなって、それで遊んでたりということはしてましたけど、結局は何かあれば料理に戻ってるんです。おばあちゃんが付いてたというのが大きいんじゃないですかね。おふくろの味というのはもちろんうちにもありましたが、おばあちゃんの味というのがあるわけですよ。だからうちはダブルで来るわけです。それでおばあちゃんは孫がかわいいから、はっきり言って何か一生懸命育てようとするんです。だからそれってやっぱり、今核家族化の中で、おばあちゃんの存在とかおじいちゃんの存在が何か飛んでしまってるんだけど、あれは一緒にしとくといいんじゃないかなと。
- 二之湯
- 確かに。うちも核家族ですけど、たまにそうやってうちの実家なり奥さんの実家なり行くと、やっぱりおばあちゃんが料理作ってくれますよね。それを食べると子どもって正直なんで、おいしいって言うんです。奥さんがちょっとむすっとするんですけども。
昨日もちょうど私が奥さんに、奥さんの実家でこの前食べたあれ、作ってよと。ちょっとおひたしみたいなやつなんですけど。今の若い女性って、若いといってもうちの奥さんはアラフォーですけど、やっぱり洋食中心なんですよね。子供たちもやっぱり洋食食べて育ってるんですけども、昨日そういう、ホウレンソウとエノキとシメジとかのおひたしを作ってくれたんです。お母さんの味を、つまりおばあちゃんの味を。ほんだらもう普段あまり食べない子供がもうそれをおかわりして、僕のまで取って、おいしい、おいしいって言って。だから、おっしゃるように教育的な。
- 服部
- 奥さんの腕がいいんですよ。
- 二之湯
- いや(笑)、あまり言うと怒られるんで。でも、そういうおばあちゃん、おじいちゃんの知恵なり経験なりを、やっぱり同居して、もしくは近くに常にコミュニケーションを取れる位置にいるというのは、実は孫の教育、もしくは現役世代の働き方とか、そういう意味でも非常にいいんだろうということで、われわれもそういう政策を取り込もうとしてるんです。


- 服部
- 今日も授業で食育について教えてきたんです
- 二之湯
- 先生はこうやって今、料理の世界だけじゃなくて、マルチなタレントというとあれですけども、いろんなメディアにも出られて活躍されてますけど、その最初のきっかけというのはどんなところにあったんですか。
- 服部
- まず学生を集めるのに、自分が旗振らないと集まらないという気になったんです。
- 二之湯
- それは先生の学校の生徒ということですね。
- 服部
- そう、これが一番大きかったです。そして学校を知ってもらうためにはどうしたらいいんだろうと。それで番組に入り込みたいなということで、料理番組、そういったものにできるだけお手伝いするようにした。最初ギャラなんかない場合があるんです。もうほとんど玉拾いみたいなもので、その玉拾いをやったから今があるみたいで。あのとき玉拾いやってなくて、はい、幾らですなんて言ってたら仕事なかったと思います。そういうもんじゃないですかね。だから何があれになるか分からないんですけども、自分としては学校に、学生を1人でも多く入ってもらうにはマスメディアというのがすごく重要だなと思ったんです。そういう時代でもあったんでしょうね。
- 二之湯
- なるほど。例えば政治家なんかでも、結構メディアに出たい人って実は多いと思うんです。名前を売るいいチャンスだし。その際に、メディアに例えば迎合じゃないですけどそういうようなスタンスと、やはり自分のビジョンというか信念みたいなものが逆に世の中に受けていくというか。メディアに出たい出たいとなるとメディアにむしろ迎合するようなところが、特にそういう世界というのはどうなんですかね。
- 服部
- それは難しい問題で、迎合している部分もあるんですよ。だけど、それは違うだろうというところも出さないと、今度は逆に使ってくれないんですよ。あいつ、迎合ばっかりしてんじゃないかって逆に見られてしまうので、その辺は微妙に自分なりにバランスを取ったはずなんです。相手も取ってくれてると思うんですけど、どっちが取られたのか取ったのか分からないんですけど。
- 二之湯
- 今、たくさんの若い学生さんが先生の学校におられるわけですけども、直接生徒さんと話をする機会というのはあるんですか。
- 服部
- 今日、今、授業をやってきました。
- 二之湯
- まだ授業も持たれてるんですか。
- 二之湯
- ちなみにどんな授業ですか。
- 服部
- 僕は今、食育基本法というのを11年前に衆参両議員立法で提案して作ることができたので、それを。今までは内閣府の食育推進室に籍を置いて食育推進評価専門委員会の座長なんですよね。北海道から沖縄まで広めてきたんで、その延長線上で、うちの学校で食をやっている者に食育を教えないというわけにはいかないだろうと。他のいろんなジャンルがあるけど、それは西欧料理の教師、日本料理の教師、中華の教師、お菓子の人とみんないますから、それにはやらせる。だから僕としては観念として食育は何であるかということを、やっぱり法律にもつなげた以上はまずうちの学生に知らせないわけにはいかないだろうと思ってやっているんです。
- 二之湯
- その中身は、食育の特にどんなところですか。
- 服部
- 簡単に言うと、3つの柱でできてまして。1つが、どんなものを食べたら安全か危険か、健康になれるか。
- 二之湯
- 食の安全ですね。
- 服部
- ええ。それの、選ぶ、選食能力。これ勉強しましょうと。2つ目が衣食住の伝承というのを。われわれは箸の持ち方とかしつけを全部覚えるんですけど。
- 二之湯
- 文化という観点ですね。
- 服部
- これは本当は家庭教育なんです。ところが家庭教育が、今、外れてきてしまったんです。だから学校で教えてくれと言うんだけど、学校の先生は逆に忙しくなってしまってそれをカバーできないので、やっぱりある程度家庭がそれを見る部分も今後考えないとまずいだろうなというのが1つ。
それで3つ目が食糧問題と環境問題です。やっぱり日本というのは自給率の低い国ですから。ドゴール大統領が45年ほど前に、自給率100%ない国は独立国とは言えないと言ったんです。そしたらフランスの周りの、今でいうEUの前身の国々が、あの当時英国は47しかなかった、それを73までもってった。
ドイツが68しかなかったのを82までもってった。フランスは105あったから肩を切って言ったわけですけど、今117です。アメリカなんか102だったのを頑張って136まで。
日本は当時73あったんですよ。それがだんだん落ちて、今、カロリーベースで39%。だけどそれはどうしてかというと、日本が頑張って農業国から脱皮して工業国になって、初めて日本というのは豊かな先進国といわれる国にはなったんですけど、空気を汚し水を汚し本当に汚い国になってしまった。だけどお金はできたんです。ところがこのところどうも中国に抜かれて3位に落ち込んだけど、このままいくと5〜6位になってしまう可能性があるんです。だからそれにならないように、どうしたらいいのかということをいつも考えるべきだし。
- 服部
- 日本の水はこんなにも素晴らしい
- 服部
- 今、海外に行って感じるのは、日本食が随分ブームになってますよね。なっているんだけれど、じゃあ日本の料理を教えてあげると言っても、彼らは珍しいなと思って見てるんですよ。だけどだからといってそれをやろうというのは少ないんです。それでお店としては、寿司は簡単にできるから寿司って言うんです。だから今、世界に和食の店が8万9,000軒あるけど、大体そのうちの85%は寿司店ですもんね。
- 二之湯
- ほとんど日本の食材を使ってない寿司屋ですよね。
- 服部
- ええ。それと、日本の水がこんなに素晴らしいということを知ってほしいんです。大体海外は全部、いわゆる水自体が、中に入り込んでるものが鉄分だったりマグネシウムとか、硬水が多いんですよ。100以上の硬水度を持ってて。例えば日本の水というのは10か20なんです。だから100以上になってくると。ボルビックというのは珍しく80%なんですけど、80でも駄目です。やっぱり10か20でないとだしが取れない。
- 二之湯
- そうですよね。米もうまく炊けないし煮物なんかもできないですしね。
- 服部
- そうですね。もうその辺を料理人が分かってなくて、向こうで一生懸命やるわけ。あんた、水が分かってなくて何でやるの? って言ってるんですよ。
それともう一つお願いがあるんですけど。向こうへ行って感じるのは。農水の仕事でわれわれ行くわけです。農水でブースを借りて日本国ということでやるわけです。それで、いろいろやってるときに、もっと他の省庁が協力してくれるとありがたいなと思ったんです。例えば外国でやってるんだから外務省はどこに関係があるの? っていうと、あまりないんですよ。外務省に呼ばれて何か仕事をしたこともあるんですけど、それは農水省と関係ないんですよ。
- 二之湯
- 縦割りになってるわけですよね。
- 服部
- だけどあれは、いわゆる日本国としてのジャパンパワーとして、みんなががっと一緒に同じことをやるような、そういう、何か垣根を取ってやってもらいたいですね。国際的な問題に対しては。
- 二之湯
- そうですね。まさに今、わが党は、2020年までに食の輸出1兆円という目標を立てているんですけども、今回さらにそれを加速化していこうということで、農林部会の中に戦略プロジェクトチームを作りまして、その輸出担当の事務局長を実は私がやらせていただいていまして。
- 服部
- そうですか。それはぜひ頑張っていただいて。
- 二之湯
- その農産物の中でも日本酒は国税庁が関係してきますので、これはまた別組織でプロジェクトチームを作って、ここも私が事務局長をやります。微力ですけども、先生のご指導も頂きながら、前倒しでどんどん日本の農産物が世界に輸出できるような環境を作っていきたいなと思っているわけなんです。
- 服部
- それは、ありがたいですね。僕は思いましたけど、日本は東南アジアとかアジアには日本の商品はそのまま持っていけるんですけど、いわゆるEU諸国はHACCP対応していないものに関しては受け入れないんですね。日本ってHACCP対応していないものが多いんです。HACCP対応すると倍以上経費がかかるからやってられないということで、今度は中国とか韓国がやり始めてるんです。
このままいくと、中国、韓国にHACCP対応した食品をどんどんやられたら、日本はこれから1兆円がちょっとまた時間がかかり過ぎるんじゃないですかね。
- 二之湯
- 本当にそういう意味では、戦略的に、かつ前倒しでどんどんやっていかなくてはいけないということはよく分かっておりますし。HACCP、イスラム圏にはハラールという認証があって、これを取らないと輸出ができないと。そういうこともしっかり踏まえたうえで、また先生、ぜひご指導いただきたいと思うんですけども。
- 服部
- ぜひよろしくどうぞ。
- 服部
- 若い人に「生き方を光らせながらやっていこう」と伝えています
- 二之湯
- 最後に、学校におられる学生さんたち、今の若い人たちを見て。今の若いのはどうだこうだという、いろいろ言われるじゃないですか。常にどの時代でもそういうことがあると思うんですけども。特にこれからは、今の若い人たちがより大人になったときというのは、高齢化している、人口が減少していると、いわゆる厳しいという観点でよく未来が語られがちだと思うんです。そういう今の学生さんの様子を見てて、どんな特徴がありますか。
- 服部
- たまたまわれわれの分野というのは、栄養士とか調理師という資格を取ることで。
- 二之湯
- 目的意識を。
- 服部
- 目的意識を持った子が多いんです。そういう意味から言うと、割としっかり見据えてきている人が多いし、趣味的にも自分は料理が好きだとか、それは大きいと思うんですよ。好きこそ物の上手なれなんで。ですから、それをさらに伸ばしてあげられるような観点の教育というのがわれわれには必要だなと、そういうことを目指してます。
- 二之湯
- やっぱり目的意識が明確な人は、当然授業に対しても真摯に取り組んでいるでしょうし。そうですよね。
- 服部
- そうですね。やっぱり必要とされる人になってくださいよって僕は最後に言うんです。
- 二之湯
- 必要とされる人。
- 服部
- それはどういうことかって言うと「ちょっと私、今日辞めさせてもらいます」と言ったら「いや、君がいないと困るんだよ」、「君はぜひ残ってください」と言われるぐらい、相手にいてほしいと思わせるぐらいのその人の存在感というもの、生き方みたいなものをいつも光らせながらやろうという話をするんです。それはなぜかと言うと「もうあんた、いなくなってもいいよ」と言われたら。
- 二之湯
- それは誰でもやる気が出ませんよね。
- 服部
- それと、失礼しますと言った途端に「あいつ、辞めてくれる、うれしい」と言うんでは困るんだ、辞めてもらっちゃ困ると思われるぐらいが大事なんで、やっぱりそういう人になりなさいと。そうすると、人間おのずと人って必ずや信用してくれるし、信頼につながるんです。
- 二之湯
- やっぱり最終的には個人の自助努力というか、自分の力で自分で生きていくんだという自立心というか、そういうものが基本的にはベースにありながら。ただそれができない、もしくはそれに対してどうしても他人と比べてスタート点が遅くなってしまう、例えばそれは家庭の環境であったり経済的な問題であったり、そういったことを取り除いていくのが政治の仕事だというふうに思います。
今日は先生から、また非常に貴重なお話も頂きました。これから実は1時から、先生と一緒に和食文化の振興についての議員連盟があります。議員立法で法改正を目指して、和食をちゃんと文化にしていこうというようなことをこれからもするんですが。
- 服部
- 各省庁も11月24日の和食の日のイベントにもっと協力的になって
- 服部
- 先生、最後に、政治というか政策的に、食のお立場で何か提言というか、そういうのはありますか。
- 服部
- 提言となると、先ほどちょっと触れたように、やっぱり日本はオールジャパンという形の中で1本に目標を絞って外交なら外交につなげていって。食はこれだけ無形文化遺産という形で2013年に11月24日を和食の日というように決めさせていただいて、われわれはそれを基に、その和食の日にいろんなイベントをやろうということで動いてきてます。去年もやったんですけど、今年もかなり大きなイベントを、実は昨日その会議があってやることになってるんです。ですからその中でやはり、それを支える日本の各省庁がもっと協力的になってほしい。ただ出てきても、このごろ聞いてはくれてるけれど。昔はそれもなかったんです。
聞いてくれるようになったんですよね。聞いてくれるけど、じゃあ一人ずつつかまえて「あなたどこまでやってくれるの」と言うと、「いや、私はただ聞きに来たもんですから」と言う。
- 二之湯
- 当事者意識がないというところがありますよね。
- 服部
- そうじゃなくて、来た以上は意識を持ってきていただきたいし、責任を持てるような立場で何か言ってほしいなと思います。生意気なことを言いますけど。
- 二之湯
- いえいえ。
- 服部
- そうしてほしいなと思います。
- 二之湯
- 分かりました。さっきから、和食は世界ブームだとかいろいろ書いていただいておりましたけれども。そういう今だからこそ、輸出額をどんどん増やしたり、観光客の誘致のためには非常に有効な戦略ですし、またその外交というかさまざまな場所に日本のアピールにもなるし。そういうことを私も自分の立場でしっかりやりたいと思ってますので、これからもご指導のほど、よろしくお願いします。
- 服部
- ぜひよろしくお願いします。いやいや、こちらこそよろしく。
- 二之湯
- 今日はどうもお忙しい中、お越しいただきましてありがとうございました。
- 服部
- ありがとうございました。
- 二之湯
- ということで、今日は1回目の『スポーツ・文化イズム!』ということでございましたけれども。これからさまざまな有識者の方にお集まりを頂いてお話をしていきたいと思いますので、また皆さん、楽しみにしてください。今日はどうもありがとうございました。
- 服部
- どうもありがとうございました。
- 会場
- (拍手)