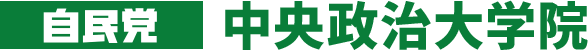9月29日(木)に中央政治大学院主催 第2回まなびとスコラを開催しました。稲田朋美副学院長を講師に、「日本のあり方を考える―日本は外国(とりわけ近隣諸国)とどう向き合うべきか?―」について講演され、その後、ディスカッションを行いました。当日は、まなびとスコラ登録者中、25名のビジネスマンや大学生が出席し、講師の発言項目に従って、盛んな意見交換を行いました。
冒頭の稲田副学院長の基調講演の要旨は以下の通りです。
◎領土問題と近隣諸国との関係について
今年の8月1日に韓国へ行って空港で入国拒否されるという経験をしました。自民党は1月の党大会で領土を守るのは自民党というメッセージを強く発信しました。民主党は領土を守らないけれども、自民党は領土を守ると訴えてきたわけです。そして、我々は竹島に行こうとしたのではなくて、鬱陵島にある独島博物館を視察するため自民党の「領土に関する特命委員会」の派遣という事でもともと訪韓が計画されました。結局、行ったけれども入国はできませんでした。韓国のマスコミが団長の新藤義孝先生に竹島はどこの国の領土かと聞きました。新藤先生は、「竹島は日本固有の領土です。韓国が不法に占拠しています」と答えたのですが、そういう事を韓国で日本の国会議員が言ったのは初めてだと思います。今は首脳会談でも外相会談でも、敢えてそのことは言わないようにしている。そんなことで本当に日韓の友好が図れるのでしょうか。そして入国できなかった理由は、表面的には韓国の入管法の公共の安全を害する恐れのある人物という規定を適用すると説明されましたが、竹島が日本の固有の領土だと主張する日本の政治家であるというのが本当の理由だと思います。では韓国はどうか。韓国は竹島に国会議員も閣僚も行っている。そして韓国の国会議員がわざわざロシアのビザで北方領土に行っている。これは、北方領土は日本の固有の領土であるにも拘らず、韓国の国会議員がロシアの領土だと認めている事になります。ここまでの事をやられている。こんな政権で日本の国が守れるのかと思います。ただ私は、連日、大騒ぎをする韓国がおかしいのか、日本がおかしいのか分からなくなりました。それは、日本では日比谷公園くらいの小さな竹島くらいあげてしまえばいいと言う。それに引き換え韓国は、あんなちっぽけな島を守るために大騒ぎをするわけです。果たしてどちらが正しいのか。竹島はあげてしまえというまさしく戦後レジームの中にあって、その脱却を訴えた安倍総理ですが、私達のそういった意識を変えようということだったと思います。日本は戦後、経済優先でやってきました。でも領土の問題や国家の名誉などは忘れてはいけないのだと思います。
北方領土については、どのような歴史的事実からも日本の領土であることは間違いありません。日ソ不可侵条約を破ってわが国の同胞をシベリアに抑留して行って、北方領土を強奪したソ連(ロシア)に何の正当性もありません。
尖閣諸島に関しては今、多くの島は日本人個人の所有地です。自民党政権下ですが、日本政府が借り上げて上陸は制限しています。これは民主党政権下でも同じですが、自分の国の領土を誰も踏む込む事が出来ないようにしているのが、日本国政府なのです。
竹島については、外務省から政府としてのパンフレットが出ています。これは自民党政権下で作ったもので、竹島の歴史的経緯や国際法上の論点が全て書かれています。日本固有の領土であって、韓国が不法占拠していますと書いてあります。ところが民主党政権になってから政府は申し合わせで「不法占拠」とは口が裂けても言いません。あろうことか江田五月法務大臣は、「この冊子が全て正しいかどうか分からない」と言って憚らないわけです。私は本当におかしな政府だと痛感しております。
中国との関係では、南京大虐殺に関わる裁判など手掛けて参りましたが、事実に反する言われのない中傷に関しては、きちんと主張しなければなりません。自分の国の名誉を自分たちで守らないで、誰が守るんでしょうか。例えば、従軍慰安婦の問題でも残念なことに、これは自民党政権下で起こったことですが、アメリカの下院で非難決議がされました。それに対して事実に反すると正式に抗議をしない国は、世界中探しても日本以外にはないと思います。
領土の問題は、きちんと教育しなければならないと思います。竹島や尖閣、北方領土の場所を知っている高校生はわずか2%以下と言われます。ところが、韓国は国定教科書の1ページ半を使って、独島が韓国の領土だと教えています。韓国の「少女時代」というグループはコンサートの最後に、独島はわが領土という歌を必ず歌うそうです。これでは全然、勝負になりません。これも政治主導の問題で、文部科学大臣が学指導要領の中に日本の領土を正しく子供に教えると書き込みさえすれば、全ての教科書は直ぐに変わります。
◎外国人地方参政権と民主党の実情について
「外国人地方参政権」の問題について民主党代表でもある野田総理は、憲法15条の問題があると言及されましたので、一応はよかったと思います。しかし野田総理は平成10年の結党時の基本理念が民主党の綱領だと答えました。その基本理念には「外国人地方参政権の早期実現」と入っています。これは自民党における自主憲法制定と同じ位置付けであり、党是と言っていい。憲法上疑義があって認めてはいけない外国人地方参政権ですが、それを認めるというのが民主党の党是です。
古屋学院長が前国会で追及されましたが、市民の党に関係する政治団体に、民主党が政権交代前3年間に2億円以上のカネを流しています。その力を借りて政権交代をしたのです。その市民の党の代表者は、選挙でこの国に革命を起こす、そのためにまず自公政権を倒すと言っています。民主党政権にし、それで日本に革命を起こすんだと。この革命とはマルクス・レーニン主義と毛沢東主義に基づく革命で、憲法を改正して象徴天皇制を廃止すると公言している。そういう人たちの力を借りて政権交代をして、民主党国会議員の公設秘書にもなっている。その党の公認候補が三鷹市議会議員選挙にも出ましたが、その父親はよど号ハイジャック事件のリーダーであり、母親は拉致実行犯、自分は北朝鮮の革命村で育ったという人物です。メディアは市民の党の疑惑にはほとんど触れていません。この状況はどういうことなのかと思います。
◎なぜ憲法を改正しなければいけないか。
理論的には、占領下で日本の主権が制限されている時に、主権国家として究極の、法治国家の中の根本的な法である憲法が改正されたのですから、そもそもの正当性の問題からしても憲法を変えなければならないと思っています。同時に、尖閣の問題でも明らかになった様に、自分の国は自分で守らないと誰も守ってくれないということです。憲法の前文には、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、この国の安全と生存を保持すると書かれています。では我々の同胞を拉致して帰そうともしない北朝鮮が、信義と公正の国と言えるでしょうか。
◎集団的自衛権について
「集団的自衛権は持っているが行使できない」というのが、今までの政府の見解でした。集団的自衛権は持っているが、憲法9条があるために、他国が攻められても日本が一緒になって武力を行使することは、9条の違反になるから出来ないというのが、自民党政権下の政府の見解でした。一方、野田総理は、「集団的自衛権は持っているしその行使もやるべきだ」と著書にも書いている。財務大臣当時も、「集団的自衛権は持っているし行使すべきだと個人的には思っている」と述べていました。先日訪米した時も、オバマ大統領に日本外交の基軸は日米同盟だと言っておられました。ならば集団的自衛権も持っているし行使もできると言えば、より安全保障上の抑止力になると思います。しかし、野田さんは「総理になった今は、個人的にはそう思うが、憲法上の問題もあるのでそうはいかない」と言っています。総理になったので政府の見解に従います、というのでは、誰が総理大臣でも引き継ぐだけだったら同じではないでしょうか。
自民党は下野したからこそ、集団的自衛権は認めるという方向へ舵を切りました。石破政調会長を中心に、集団的自衛権の行使を認める議員立法を提出するため議論しています。また、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が名実ともに主権を回復した4月28日を「主権回復記念日」に制定し祝日にするという議員立法も谷垣総裁も了承のうえで自民党から出しています。そういう意味からも、戦後レジームからの脱却だと安倍先生が言われていた事を、もう一度自民党の旗にして、「自分の国は自分で守る」「自分の国の名誉は自分で守る」と、当たり前のことですが、それをしてこなかった日本を変え、もう一度、普通の国にしたいと思っております。
基調講演の後、出席者を交えて以下の項目について建設的な意見交換が交わされました。
◎近隣諸国への対応・領土問題について
「日本は近隣諸国に対して、あまりにも弱腰だ」
「政府・与党・野党と立場の違いでいう事が違う」
「諸外国の軍事防衛の実情をもっと知らせるべきではないか」
「領土問題では、相手国に抗議されっ放しではないか」
「正当性があるなら、国際社会に訴えるべき」
「領土問題についての中国、韓国、ロシアの認識の違いはどうなのか」
「主権を主張するだけで解決できるのか」
「解決に向けた方法はあるのか」
◎憲法改正について
「96条の改正条項の見直しについて」
「憲法改正に対する国民の意識について」
「憲法改正の必要性が曖昧」
「改正後のビジョンや国民生活にどのように変わるのかピンとこない」
「憲法改正と言っているだけでは遠い出来事に聞こえる」
◎教育問題
「教科書は自虐性に偏り過ぎているのではないか」
「イギリスの教育・教科書改革を参考にバランスよくすべきではないか」
「教育公務員特例法の改正で罰則規定を設けるべきではないか」